スコアリングルールの作り方と失敗要因|成果を出すための設計・運用プロセスとSLA構築の重要性
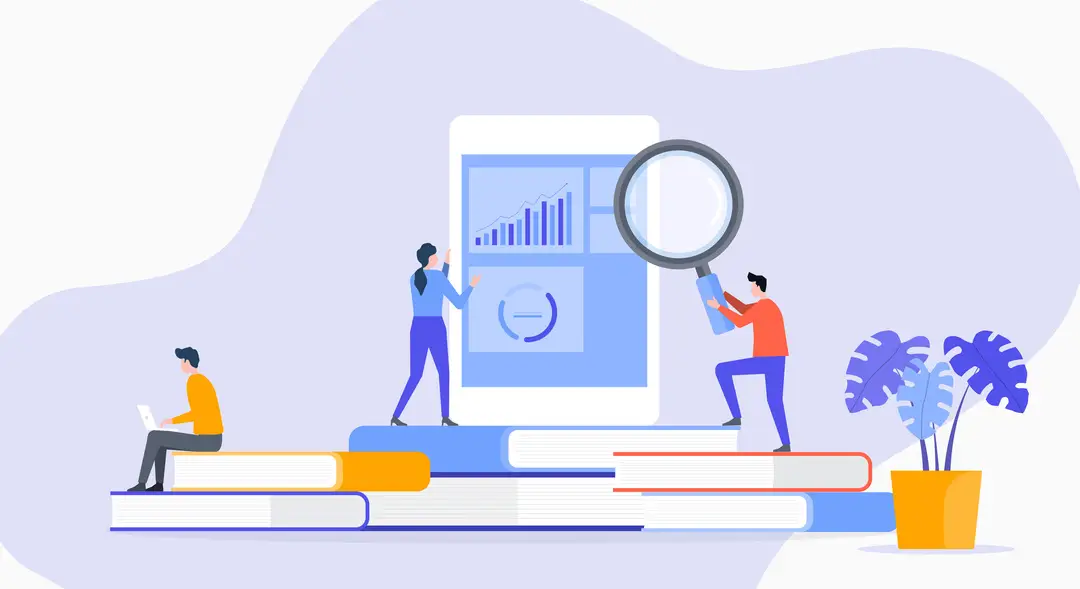
MAツールの導入・活用の相談はSells upへ。
MAツールの導入や、導入後の成果最大化に課題をお持ちでしたら、ぜひSells upにご相談ください。50社以上の導入・活用を支援してきた担当者が貴社の状況・目標に向き合い、最適なツールの導入プラン / 統計知識を用いた活用プラン描き、戦略策定から実装 / 実行 / 効果測定までをご支援いたします。
BtoBマーケティングにおいて、リードスコアリングはマーケティングオートメーション(MA)ツールの中核機能であり、リードの質を評価し、営業活動の優先順位を決定するための重要な仕組みです。しかし、多くの企業がその導入と運用に苦戦しています。
「スコアリングルールが作れない」という課題には、2つの側面が存在します。
1つは、スコアリングの対象項目や点数配分の目安といった「具体的な作成手順が分からない」というケース。もう1つは、ルールを作成・運用してみたものの、「スコアが高いリードが必ずしも質の高いリードではない」「営業部門から信頼されない」といった、「有効なルールが作れない」というケースです。
後者の課題の核心は、多くの場合、ルールの作り方そのものではなく、組織的な連携やデータ基盤の整備といった、ルール作成以前の段階にあります。
本記事では、成果に繋がるスコアリングルールを作成するための全体プロセスを提示し、各ステップにおける具体的な手順、失敗を回避するためのポイント、そしてデータに基づく改善手法までを体系的に解説します。
スコアリングルール作成の全体プロセス(5ステップ)
有効なスコアリングルールは、体系的なアプローチで構築し、運用を通じて改善していく必要があります。全体像は以下の5つのステップで構成されます。
Step.1:基盤の構築(SLAとMQL定義)
スコアリングが失敗する主な原因は、営業とマーケティングの連携不足です。最初のステップとして、両部門間の合意を明文化したSLA(Service Level Agreement)を構築し、MQL(Marketing Qualified Lead:マーケティングが認定した質の高いリード)を定義します。
Step.2:データ整備
スコアリングの精度はデータの品質に依存します。不正確・不完全なデータからは有効なスコアは算出されません。MAやSFA/CRM内のデータをクレンジングし、標準化します。
Step.3:スコアリングモデルの設計
SLAで合意したMQL定義に基づき、具体的なスコアリングモデルを設計します。リードの「属性(Fit:適合度)」と「行動(Intent:関心度)」の2軸で評価するモデルが基本です。最初はシンプルなモデルから開始します。
Step.4:実装とテスト
設計したモデルをMAツール上に実装します。実装後は、意図した通りに動作するか、スコア分布が適切かをテスト・検証します。
Step.5:運用と継続的な改善(最適化)
運用開始後、実際の営業成果データを分析し、スコアと成果の相関関係を評価します。この分析結果に基づき、定期的にルールを見直し、精度を高めていく継続的な改善サイクルを回します。
以下、各ステップについて具体的に解説します。
Step.1:戦略的基盤の構築 - 営業と連携するSLA構築
スコアリングルール作成の議論を始める前に、営業とマーケティングが共通の目標と認識を持つ必要があります。そのための仕組みがSLAです。
SLAとは
SLAとは、マーケティング部門と営業部門が互いに対して行うコミットメント、責任、そして共有目標を定義した合意書です。
SLAが存在しない場合、「有望なリード」の定義が各部門の主観に委ねられます。その結果、マーケティングはリードの「量」を、営業はリードの「質」を重視し、対立構造が生まれやすくなります。SLAは、スコアに共通の意味と価値を与え、両部門の共通言語として機能します。
【Sells upの視点】スコアリング成功のポイントは、ルール設計の「前」にある
Sells upはこれまで多くの企業をご支援してきた経験から、リードスコアリングの成否を分ける重要な要素は、ルールの精緻さではなく、その前段階にある「営業とマーケティングの戦略的な連携」であると考えています。
成果を出し続けている企業は、スコアリングルールを作る前に、「どのような顧客をターゲットにするのか」「どのような状態のリードを営業に渡すのか」を徹底的にすり合わせています。SLAの作成は、単なる文書作成作業ではなく、両部門間の期待値を明確にし、共通の目標に向かって協力するための戦略的な対話をするプロセスです。
営業と連携したMQL定義ワークショップの進め方
SLAの核となるMQLの定義は、関係者が参加する「MQL定義ワークショップ」で作成することがお奨めです。
1. 関係者の招集と過去データの分析
営業マネージャー、営業担当者(特にトップセールス)、マーケティング責任者、MA運用担当者などを招集します。
次に、議論を主観的な意見に終わらせないために、過去に成約した案件データを分析し、成功した顧客に共通する特徴を洗い出します。
属性情報:業種、従業員規模、役職など
行動情報:成約前にどのコンテンツをダウンロードしたか、どのウェブページを閲覧したかなど
2. Fit(適合度)とIntent(関心度)の軸を定義する
分析データと営業部門の知見を基に、理想的な顧客プロファイル(ICP:Ideal Customer Profile)を定義します。そして、MQLを定義するために、以下の2つの軸を設定します。
1. Fit(適合度):リードが誰であるか
リードがICPにどれだけ合致しているかを評価します。等級(例えばA、B、C、D)を設定する方法が一般的です。
例:A(最適:ターゲット業種、決裁権を持つ役職)、B(良好)、C(検討可)、D(対象外)
2. Intent(関心度):リードが何をしたか
リードの行動から購買意欲の高さを見極めます。行動が購買プロセスのどの段階に位置するかを考慮します。
例:高関心度(価格ページの閲覧)、中関心度(ウェビナー参加)、低関心度(ブログ記事の閲覧)
これら2つの軸を組み合わせ、MQLの定義を言語化します。
定義例:「MQLとは、プロファイル等級がAまたはBであり、かつ、関心度スコアが100点以上のリードである」。
3. リードの引き渡しとフィードバックルールの設計
MQLが定義されたら、その後の運用プロセスを設計します。
引き渡しのトリガーと方法:MQLの条件を満たしたリードを、どのような仕組みで営業部門に通知・割り当てるかを定義します。(例:CRM上でのタスクの自動生成)
営業の対応までの時間:引き渡されたMQLに対し、営業部門が何時間以内に最初のアクションを起こすかを定義します。Sells upでは、10分以内の対応をお奨めしています。
フィードバックループ(差し戻しプロセス):商談化に至らなかったリードを、営業が明確な理由(例:時期尚早、予算不足)と共にマーケティングに差し戻すプロセスを定義します。このフィードバックは、ルール改善のための貴重なデータとなります。
SLA設計ワークシート
SLAの議論を円滑に進めるためには、以下のようなワークシートを活用します。
項目内容1. 合意の概要と目標・本SLAの目的(例:商談化率の向上) ・共有する事業目標(KPI)2. MQLの定義・プロファイル等級(Fit)の基準: - Aランク:[業種、役職、企業規模などの具体的基準] ・関心度スコア(Intent)の基準: - MQLと認定される最低スコア(例:100点)3. リード引き渡しプロセス・トリガーとシステム連携方法 ・連携する情報(スコアの内訳、直近の行動履歴など)4. 営業フォローアップ規約・初回対応時間:[例:24] 営業時間以内 ・フォローアップ最低基準:最低 [例:4] 回のコンタクト5. リードの差し戻し(リサイクル)プロセス・差し戻し基準と方法6. レポーティングと定例会議・共有KPI(MQL数、商談化率、受注率)と会議頻度
Step.2:データ基盤の整備 - スコアリング精度を高めるデータ要件
SLAが整ったら、次はスコアリングの精度を左右するデータ基盤を整備します。不完全なデータや質の低いデータは、スコアリングモデルを機能させにくくします。
属性(Fit)スコアリングに必要なデータ品質
Fitスコアリングは、リードの属性情報に基づいて行われます。特に以下の点に注意が必要です。
データの完全性:スコアリングに必要な項目(業種、企業規模、役職など)が欠落していないか。欠落率が高い場合、フォームの入力項目を見直す、あるいは外部のデータ補完サービスを利用するなどの対策が必要です。
データの標準化(名寄せ・正規化):役職名の表記揺れ(例:「部長」「マネージャー」「Mgr」)や企業名の表記揺れ(例:「株式会社ABC」「(株)ABC」)があると、正しいスコアリングができません。MAやCRM内でデータを標準化するルールを整備します。
データの正確性と鮮度:古い情報や誤った情報が登録されていないか。定期的なデータクレンジングが必要です。
行動(Intent)スコアリングに必要なデータ要件
Intentスコアリングは、リードの行動履歴データに基づいて行われます。
適切な行動データの取得:MAツールがウェブサイトの閲覧履歴、メールの開封・クリック、フォーム送信などの行動データを正しくトラッキングできているかを確認します。特に、重要なページ(価格ページ、事例ページなど)のトラッキング設定漏れがないか注意が必要です。
信頼性の高いシグナルの利用:メールの開封といったシグナルは、セキュリティソフトによって自動的にトリガーされる可能性があり、信頼性が低い場合があります。フォーム送信や特定のページ閲覧など、より意図の強い行動データに重点を置くことが推奨されます。
Step.3:スコアリングモデルの設計
土台とデータ基盤が整備されたら、具体的なスコアリングモデルの設計に進みます。ポイントは、最初から複雑にせず、シンプルなモデルから始めることです。
2軸評価モデル(Fit × Intent)の基本構造
Step.1で定義した通り、リードの価値を「Fit(適合度)」と「Intent(関心度)」の2つの異なる軸で評価します。
この2軸で評価することで、「熱心だがターゲット外(低Fit、高Intent)」と「購買意欲の高い決裁者(高Fit、高Intent)」を明確に区別し、営業リソースを後者に集中させることが可能になります。
Fit(適合度)スコアの設計と項目例
Fitスコア(グレーディングとも呼ばれます)は、ICPにリードがどれだけ合致しているかを評価します。
役職/役割:決裁者か、担当者か
業種:ターゲットとする業種か
企業規模:従業員数や売上高がターゲット範囲内か
【Fitスコア設定例】
業種がターゲット業界:+15点
従業員数が100名以上:+10点
役職が部長・課長クラス:+15点
Intent(関心度)スコアの設計と重み付け
Intentスコアは、リードの行動に基づいて関心の度合いを評価します。行動の裏にある「意図の強さ」に応じて点数に重み付けを行うことがポイントです。
高関心度アクション(目安:+15~+50点)
購買意欲が高いことを意味する行動です。
デモリクエスト/営業への問い合わせフォーム送信:購買シグナル。多くの場合、営業へ通知すべきです。
価格ページの閲覧:具体的な導入検討層と考えられます。
BoFu(Bottom of the Funnel)コンテンツのダウンロード:導入事例、製品比較資料など。
中関心度アクション(目安:+5~+15点)
情報収集を積極的に行っている段階の行動です。
ウェビナーへの参加:単なる「登録」と、実際の「参加」を区別してスコアリングすることが重要です。
MoFu(Middle of the Funnel)コンテンツのダウンロード:ホワイトペーパー、詳細なガイドブックなど。
高価値ページの閲覧:製品機能紹介ページなど。
低関心度アクション(目安:+1~+5点)
認知・興味段階の初期的な行動です。
ウェブサイトへの訪問/一般的なページの閲覧
メールの開封・クリック:補助的な指標として慎重に扱います。
【Sells upの視点】統計的解析による客観的なスコアの重み付け
多くの企業が「価格ページの閲覧は何点にすべきか?」といった点数設定に悩んでいます。スコアの点数設定はあくまで一般的な目安であり、感覚的に点数を設定してしまうと、モデルの精度低下の原因となります。
Sells upでは、自社にとって最適なスコアリングモデルを構築するために、過去の受注データを用いた統計的な解析を推奨しています。どの行動がどれだけ受注確率に影響を与えたかを客観的に算出し、その影響度に応じて点数を配分することで、根拠のあるスコアリングモデルを構築できます。
統計的解析(ロジスティック回帰分析)の活用
具体的には、ロジスティック回帰分析の手法を用います。これは、各行動(説明変数)が受注(目的変数)に与える影響度(寄与度)を定量的に分析する手法です。
この分析により、「価格ページの閲覧」が「ホワイトペーパーのダウンロード」よりも何倍、受注確率を高めるのかを数値で把握できます。この客観的な影響度に基づいてスコアの重み付けを行うことで、担当者の勘や経験に頼らない、精度の高いスコアリングが可能になります。
データに基づいた客観的な基準設定は、営業部門に対してルールの妥当性を説明する際にも説得力を高め、信頼されるスコアリングを実現するポイントです。
ネガティブスコアリングとBANT条件の活用
ネガティブスコアリング(減衰ルール)
スコアを加算するだけでなく、減算するルールも重要です。これにより、不適切なリードを自動的にフィルタリングします。
採用ページの閲覧:求職者である可能性が高い。(例:-50点)
メールマガジンの購読解除(例:-20点)
競合他社のドメインからのアクセス(例:-100点)
BANT条件による定性情報の統合
スコア(定量情報)だけでは判断しきれないリードの質を補完するために、定性的なフレームワークである「BANT条件」を活用します。
B (Budget):予算
A (Authority):決裁権
N (Need):必要性
T (Timeframe):導入時期
これらの情報を、フォームの設問項目(例えば「ご検討の時期」)として組み込み、回答内容をスコアリングの加点条件としたり、営業への引き渡し情報として付加したりすることで、リード評価の精度を高めることができます。
Step.4:実装とテスト
設計したスコアリングルールをMAツールに実装し、意図した通りに動作するかを検証します。
主要MAツール別実装のポイント
使用しているツールの特性を理解することが不可欠です。
【主要MAツール スコアリング機能比較】
機能HubSpotSalesforce Account Engagement (旧Pardot)Marketo Engageコアモデル単一スコアプロパティに条件を設定スコア(関心度)とグレード(適合度)を分離複数のカスタムスコアフィールドを作成・管理Fit vs Intent単一スコア内で混在。カスタムプロパティで擬似的なグレード管理が可能。グレードでFit、スコアでIntentを管理するネイティブな2軸モデル。複数のスコアフィールドを組み合わせて柔軟な2軸モデルを構築。複数製品のスコアリング複数のスコアプロパティを作成可能。スコアリングカテゴリ機能により、製品別の関心度を追跡。スマートキャンペーンとセグメンテーションを駆使して構築。カスタマイズ性直感的で設定しやすいが、複雑なロジックには限界がある。標準機能がBtoBのベストプラクティスに沿っている。柔軟性が高く、スマートキャンペーンで複雑なロジックも実装可能。
HubSpot
標準の「HubSpotスコア」プロパティで加点・減点条件を設定します。Fit(適合度)を評価するために、カスタムプロパティを作成し、その値に基づいてスコアリングを行うことも可能です。
Salesforce Account Engagement (旧Pardot)
スコア(Intent)とグレード(Fit)が明確に区別されており、2軸モデルを実装しやすい設計です。標準で用意されているベースラインのスコアリングルールをカスタマイズすることから始めます。
Marketo Engage
「行動スコア」「属性スコア」といったカスタムのスコアフィールドを複数作成し、管理することが推奨されます。スマートキャンペーンを使って柔軟にスコアを増減できます。
実装後のテストと検証プロセス
スコアリングモデルを本番稼働させる前に、必ずテストを実施します。
1. テストリードによる動作確認
テスト用のリードを作成し、設計したシナリオ通りの行動(フォーム送信、Webページ閲覧など)を実行します。各行動に対して、意図した点数が正しく加算・減算されるかを確認します。
2. 過去データによるシミュレーション
過去のリードデータに対して新しいスコアリングルールを適用し、スコア分布をシミュレーションします。受注に至ったリードが高スコアに、失注したリードが低スコアになっているかを確認し、モデルの妥当性を評価します。極端なスコア分布になっている場合は、ルールの見直しが必要です。
3. 営業部門との共同レビュー
テスト結果を営業部門に共有し、スコアが付与されたリードのプロフィールや行動履歴を見ながら、認識のズレがないかを最終確認します。
Step.5:運用と継続的な改善プロセス(最適化)
リードスコアリングモデルの構築はスタートラインです。「一度設定したら終わり」という状態は、モデルの有効性の低下を招きます。成果を出し続けるためには、データに基づき継続的に改善する仕組みが必要です。
スコア減衰の実装:スコアの鮮度を保つ
顧客の関心は時間とともに変化します。スコア減衰の仕組みがないと、過去に活発だったが現在は関心が薄れているリードが高いスコアを維持し続け、現在ホットなリードよりも優先されてしまう事態が起こります。
時間経過による関心度の低下をモデルに組み込む必要があります。
時間ベースの減衰:一定期間、活動が見られない場合に、自動的にスコアを減点します。
実装例:「最終活動日から30日が経過するごとに、スコアを25点減点する」。
スコアのリセット:長期間(例えば180日間)活動がないリードに対しては、スコアをリセットします。
データ駆動の改善サイクル(クローズドループ・レポーティング)
最初に設定したスコアリングモデルは仮説です。この仮説を検証するためには、実際の営業成果(売上)とスコアリングデータを結びつけて効果測定し続けることが不可欠です。
改善サイクルの実行
1. 追跡(Track)
引き渡したMQLが、最終的にどのような結果(商談化、受注、失注)になったかをCRM/SFA上で追跡します。
2. 分析(Analyze)
受注案件と失注案件のデータを比較分析します。特に、受注案件に共通して見られた行動や属性は何かを特定します。
3. 行動(Act)
分析結果に基づき、スコアリングモデルを調整します。例えば、成約に貢献している行動のスコアを上げ、貢献していない行動のスコアは下げます。
このサイクルを回し続けることで、スコアリングモデルは自社のビジネスに最適化された高精度の予測モデルへと改善されていきます。
【Sells upの視点】継続的な改善における統計的解析の活用
改善サイクルにおいても、統計的な解析が精度向上に貢献します。運用を通じて蓄積されたデータ(MQLのその後の成約状況)を分析し、初期に設定したスコアリングルールの妥当性を検証します。
Step.3で紹介したロジスティック回帰分析などの統計手法を用いて、どの行動が受注にどれだけ影響を与えているかを継続的に再評価します。これにより、市場の変化や顧客行動の変化に合わせて、スコアの重み付けを動的に最適化することが可能になります。このデータに基づいた客観的な改善プロセスこそが、スコアリングモデルの精度を持続的に高めるポイントです。
定期的なレビュー会議の制度化
継続的な改善を担保するためには、改善プロセスを組織の正式なプロセスとして制度化することが重要です。四半期に一度など、定期的に「スコアリングレビュー」の場を設けます。
推奨されるアジェンダ
KPIレビュー:MQLから受注までの転換率など、目標に対する達成状況を評価します。
データ分析報告:データ分析(統計的解析を含む)から得られた、受注に相関する行動パターンの報告。
営業部門からの定性的フィードバック:MQLの質に関する所感や、営業プロセス上の課題共有。
モデル修正案の討議:分析結果とフィードバックに基づき、ルールや閾値の変更点について両部門で連携を図る。
スコアリングが適さないケースと代替アプローチ
スコアリングは万能ではありません。自社のビジネスモデルやリードの量によっては、他のアプローチが効率的な場合もあります。
スコアリングが不要または過剰となるシナリオ
リードの量が少ない場合:月に数十件程度のリードしか獲得できず、営業担当者が全件を手動で確認できる場合。
ABM(アカウントベースドマーケティング)に注力している場合:個々のリードのスコアよりも、ターゲットアカウント全体のエンゲージメントが重要になる場合。
営業サイクルが短い場合:検討期間が短い商材で、即時対応が求められる場合。
代替アプローチ:トリガーベースのルーティング
点数を積み重ねるのではなく、特定の「決定的瞬間」を捉えてアクションを起こすアプローチです。
例:
リードが価格ページを30日以内に3回以上訪問したら、即座に担当営業へ通知する。
特定の導入事例をダウンロードしたリードを、インサイドセールスチームの架電リストに自動で追加する。
このようなアプローチは、ルールがシンプルで、リードの「今」の関心に即座に対応できる利点があります。
まとめ:スコアリングは営業と連携し、データに基づき「育てる」仕組み
「スコアリングルールが作れない」という課題の背景には、技術的な操作方法の欠如だけでなく、成果に繋がる有効なモデルを構築・運用できないという問題もあります。
成功するリードスコアリングとは、単一のマーケティング施策ではなく、営業との連携を前提とした、データ駆動型の継続的な改善プロセスそのものです。
成果を出すためには、以下のポイントが不可欠です。
組織的な土台作り(SLA):スコアリングルールの作成を、マーケティング部門内のタスクから、営業部門との共同事業へと位置づけ、MQLの定義と運用ルールを合意する。
データ品質の確保:データクレンジングや標準化により、スコアリングの精度を高めるデータ基盤を整備する。
体系的な設計:「Fit(適合度)」と「Intent(関心度)」の2軸で評価し、可能であれば統計的解析(ロジスティック回帰分析など)を用いて客観的な根拠に基づいた点数設定を行う。
継続的な改善サイクル:「一度設定したら終わり」ではなく、スコア減衰とクローズドループ・レポーティングによる継続的な改善サイクルを回す。
スコアリングは「作って終わり」の設定ではなく、会社全体で対話を重ねながら“育てていく”仕組みです。ぜひ本記事で解説した5つのステップを参考に、貴社でも成果に繋がるスコアリング運用の仕組みづくりに取り組んでください。
MAツールの導入・活用の相談はSells upへ。
MAツールの導入や、導入後の成果最大化に課題をお持ちでしたら、ぜひSells upにご相談ください。50社以上の導入・活用を支援してきた担当者が貴社の状況・目標に向き合い、最適なツールの導入プラン / 統計知識を用いた活用プラン描き、戦略策定から実装 / 実行 / 効果測定までをご支援いたします。
CONTACT







