SATORIスコアリング完全攻略ガイド|設定方法から営業連携まで、成果を出すための実践術
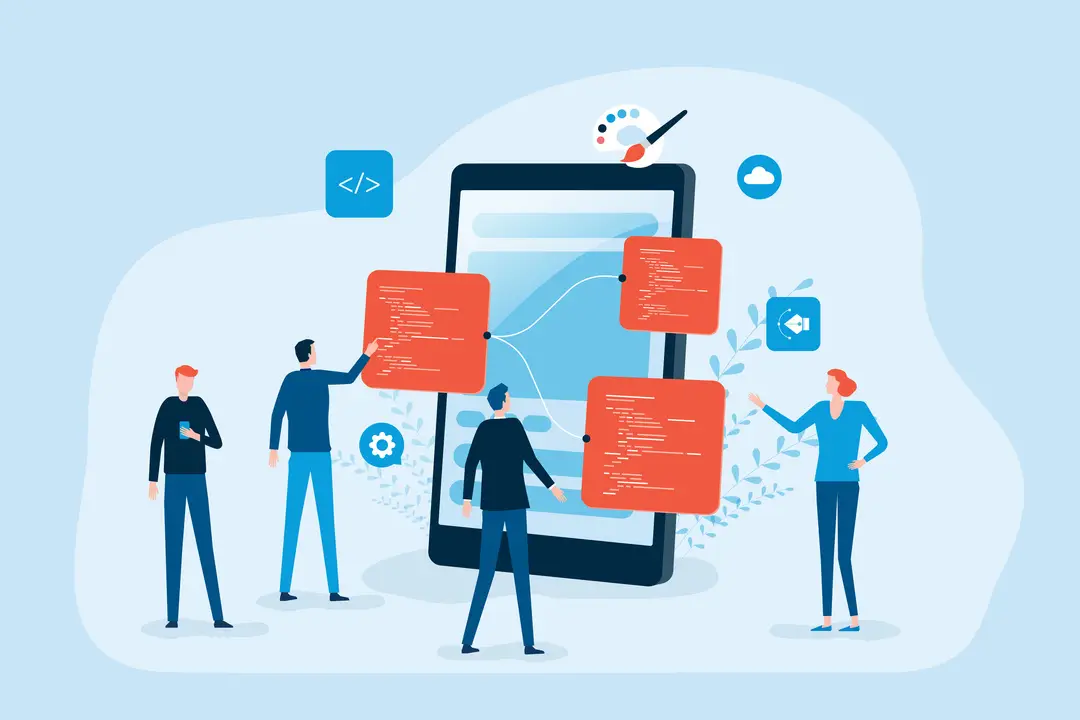
MAツールの導入・活用の相談はSells upへ。
MAツールの導入や、導入後の成果最大化に課題をお持ちでしたら、ぜひSells upにご相談ください。50社以上の導入・活用を支援してきた担当者が貴社の状況・目標に向き合い、最適なツールの導入プラン / 統計知識を用いた活用プラン描き、戦略策定から実装 / 実行 / 効果測定までをご支援いたします。
なぜ今、SATORIで「スコアリング」に取り組むべきなのか?
「とりあえずリードを渡す」運用がもたらす、静かな機会損失
マーケティング部門が獲得した見込み顧客(リード)を、そのまま営業部門へ引き渡す。多くの企業で日常的に行われているこのプロセスには、実は見過ごせない機会損失が潜んでいます。
リード一人ひとりの興味関心の度合いや検討段階は様々です。それにもかかわらず、質にばらつきがあるリストを渡された営業担当者は、見込みの薄い相手にも貴重な時間を割かざるを得ません。結果として、本当に注力すべき有望なリードへのアプローチが遅れ、商談化率や成約率が伸び悩むという事態に陥りがちです。
このような状況が続けば、営業部門から「マーケティング部門からのリードは質が低い」という不満の声が上がるのも無理はありません。これは単なる部門間の軋轢に留まらず、会社全体の成長を鈍化させる大きな要因となり得ます。
営業とマーケティングの対立をなくす「共通言語」としてのスコアの価値
営業とマーケティング、それぞれの部門が考える「有望な見込み客」の定義が異なっていると、連携はうまくいきません。この認識のズレこそが、多くの企業が抱える根深い課題です。
SATORIのスコアリング機能は、この部門間の溝を埋めるための「共通言語」として非常に有効です。Webサイトの閲覧履歴や資料請求といった顧客の行動を「スコア」という客観的な数値で評価することで、「スコアが100点を超えたらホットリードとする」といった具体的な基準を共有できます。
これにより、両部門が同じものさしでリードの優先度を判断できるようになり、感覚的な対立や誤解をなくすことが可能です。スコアリングは、データに基づいた建設的な対話を生み出し、組織全体で顧客に向き合うための第一歩となるのです。
SATORIスコアリング機能の基本を理解する
SATORIで実現できるスコアリングとは?その仕組みを解説
SATORIのスコアリング機能とは、見込み顧客のWebサイト上での行動や、メルマガへの反応といった様々な接点に応じて、あらかじめ設定した点数(スコア)を自動で加算・減算する仕組みです。
例えば、「料金ページの閲覧は+30点」「資料請求フォームの送信は+50点」といったルールを設定することで、顧客の興味関心や購買意欲の高まりを数値で可視化します。これにより、確度の高いリードを客観的なデータに基づいて特定し、最適なタイミングで営業へ引き渡すことが可能になります。
さらに、スコアの変動をトリガーとして、「合計スコアが100点に達したリードに特別なインナーオファーのメールを送る」といった、一人ひとりの顧客に合わせたきめ細やかなアプローチを自動化することもできます。スコアリングを使いこなすことは、マーケティング活動の成果を最大化し、営業部門との連携を改善するための鍵といえるでしょう。
「共通設定」と「個別設定」の違いと戦略的な使い分け
SATORIのスコアリングには、「共通設定」と「個別設定」という2種類の設定方法があります。それぞれの特性を理解し、戦略的に使い分けることが、精度の高いスコアリングを実現する上で非常に重要です。
共通設定:スコアリングの「土台」を築く
共通設定は、「メール開封は一律+10点」のように、アクションの種類ごとに一律でスコアを設定する機能です。まずはこの共通設定で、基本的な顧客行動に対する評価の骨格を作ります。全体のベースとなるルールを定めることで、運用をシンプルに始めることができます。個別設定:スコアリングの「精度」を高める
個別設定は、「“特定”の料金プランAの資料請求フォームからの登録に限り+500点」のように、より細かい条件を指定してスコアを調整する機能です。特に商談化に繋がりやすいと分かっている重要なアクションに対して、重点的に高いスコアを付与するために活用します。
まずは共通設定で全体の土台を固め、運用しながら得られたデータや営業からのフィードバックを基に、個別設定でより細やかなチューニングを加えていく。この段階的なアプローチが、スコアリングを成功させるための定石です。
【図解】明日から実践!SATORIスコアリング設定マニュアル
設計で9割決まる!最初に行うべき営業との「ホットリード」定義のすり合わせ
スコアリング運用を成功させる上で、最も重要なプロセスが、営業部門との「ホットリード」定義のすり合わせです。ツールを操作する前に、まず両部門で「どのような状態の顧客を、営業がアプローチすべき『ホットリード』と呼ぶのか」という共通認識を確立する必要があります。
具体的には、以下のような観点でディスカッションを行い、合意形成を目指しましょう。
行動:過去の受注顧客は、商談前にどのようなWebページを閲覧し、どんな資料をダウンロードしているか(例:導入事例、料金ページ、機能詳細ページなど)
属性:どのような業種、企業規模、役職の担当者からの問い合わせが、成約に結びつきやすいか
タイミング:資料請求から何日以内のアプローチが最も効果的だったか、Webサイトへの再訪頻度は、検討度合いとどう関係しているか
失注理由:逆に、商談化したものの失注したケースでは、どのような特徴があったか、その知見をスコアの減点ルールに活かせないか
このすり合わせを通じて、営業担当者が「この基準で抽出されたリードなら、自信を持ってアプローチできる」と納得できるルールを作ることが、スコアリングが形骸化しないための絶対条件です。
【BtoB SaaS向け】コピーしてすぐに使えるスコアリング設定テンプレート
ここでは、BtoB SaaS企業でよく使われるスコアリング項目の一例を紹介します。自社の状況に合わせてカスタマイズし、まずはシンプルな構成からスタートするのがおすすめです。
アクション/属性 | カテゴリ | 推奨スコア |
|---|---|---|
料金ページの閲覧 | 興味・行動 (High Intent) | +30 |
導入事例のダウンロード | 興味・行動 (High Intent) | +50 |
デモ申込フォーム送信 | 興味・行動 (Critical Intent) | +90 |
ウェビナー参加 | 興味・行動 (Medium Intent) | +20 |
役職:「部長」以上 | 属性 | +30 |
30日以内の再訪問 | 活性度 | +20 |
競合ドメイン | 属性 | -500 |
コール拒否タグ付与 | 状態 | -500 |
このテンプレートをもとに、まずは主要な行動や属性にスコアを割り当て、運用しながら随時見直していくことが重要です。
スコア定義の具体的な登録手順
SATORIのスコアリング設定は、管理画面から直感的に行うことができます。ここでは「共通設定」と「個別設定」の登録方法を、目的と合わせて解説します。
基本的な行動を捉える「共通設定」の登録方法
まずは、全てのリードに適用される基本的なルールを「共通設定」で定義します。
Step.1:管理画面左メニューの「設定」から「スコア定義」を選択します。
Step.2:「共通設定」タブが開かれていることを確認します。
Step.3:各アクションタイプ(例:フォーム送信、メール開封)の右側にある「編集」ボタンをクリックします。
Step.4:加算・減算したいスコア値を入力し、「登録」を押して保存します。これにより、例えば「どのメールマガジンであっても、開封すれば一律で+3点」というルールが適用されます。
重要アクションを捉える「個別設定」の登録方法
次に、特に重視したい特定の行動に対して、「個別設定」で重み付けを行います。
Step.1:同じく「スコア定義」画面で「個別設定」タブに切り替えます。
Step.2:画面右上の「+」ボタンをクリックし、新規登録画面を開きます。
Step.3:「スコア名」(例:料金ページ閲覧スコア)と、加算したいスコア値を入力します。
Step.4:対象となるアクションタイプ(例:ウェブアクセス)と、条件(例:URLフィルタで料金ページのURLを指定)を細かく設定します。
Step.5:「登録」ボタンを押して保存します。これで、「料金ページを閲覧したリードに限り、特別に+30点を加算する」という、より精度の高いルールが完成します。
スコアリングを“宝の持ち腐れ”にしない!成果を出し続ける運用術
SATORIスコアリングでよくある3つの失敗例とその解決策
失敗例1:競合やパートナー企業に高いスコアが付いてしまう
自社サイトを熱心に調査する競合他社やパートナー企業に高いスコアが付与され、営業がアプローチしてしまうのは典型的な失敗例です。
解決策:判明している競合・パートナー企業のドメインをリスト化し、「該当ドメインからのアクセス時はスコアを大幅に減点する」という個別設定を追加しましょう。また、四半期に一度は高スコアリードのリストを目視で確認し、ノイズとなるドメインを除外リストに追加していく、という運用ルールを設けることも有効です。
失敗例2:スコアは高いのに、一向に商談化しないリードが溜まっていく
Webサイトの閲覧回数など、行動の「量」だけを評価していると、単なる情報収集目的の担当者や、既に顧客となっているユーザーのスコアが過剰に高くなってしまうことがあります。
解決策:行動の「質」を見極めることが重要です。「料金ページ」や「導入事例」といった購買意欲の高いページへのアクセスには高いスコアを、一方で「採用情報」や「ブログ記事」の閲覧は低めのスコアに設定するなど、行動の意図を汲み取った設計に見直しましょう。また、「直近30日以内の行動のみを評価対象とする」など、行動の鮮度(活性度)を考慮に入れることも精度向上に繋がります。
失敗例3:営業部門がスコアを信用せず、結局使われなくなる
スコアリングの基準が営業担当者の現場感覚とズレていると、「このスコアは当てにならない」と判断され、せっかくの仕組みが全く活用されなくなってしまいます。
解決策:設計段階で営業を巻き込むことはもちろん、運用開始後も定期的にフィードバックをもらう場を設けることが不可欠です。「スコア100点でパスしたリードの商談化率」といった定量データに加え、「最近パスされる高スコアリードは、まだ検討の初期段階のことが多い」といった定性的な意見も収集し、スコア基準を柔軟にアップデートし続ける姿勢が、営業から信頼される「ホットリード」につながります。
スコアの精度を継続的に高めるためのPDCAサイクルの回し方
スコアリングは、一度作ったら完成するものではなく、継続的に改善していく必要があります。以下のPDCAサイクルを定期的に(例えば四半期に一度)回すことで、その精度を着実に高めていくことができます。
Plan(計画):営業部門と連携し、現状の課題に基づいたスコアリングの仮説(どの行動が受注に繋がりそうか)を立て、スコアのルールを設計・見直します。
Do(実行):新しいスコアリングのルールをSATORIに設定し、一定期間運用します。
Check(評価):運用期間終了後、「設定した閾値以上のスコアで商談化したリードの割合」や「受注に至ったリードの平均スコア」などを分析します。営業担当者へのヒアリングも行い、スコアと現場感覚のズレがないかを確認します。
Action(改善):評価結果に基づき、スコアの加点・減点ルールや、ホットリードの閾値を見直します。そして、次のPlan(計画)へと繋げます。
この地道な改善サイクルこそが、スコアリングを自社のビジネスに最適化された、本当に価値ある仕組みへと育てていくのです。
【Sells upの視点】スコアリングの真価は「営業連携の深化」にある
スコアは「引き渡しの基準」ではなく、顧客理解を深める「対話のきっかけ」
私たちは、スコアリングを単なる「リードを引き渡すための基準点」と捉えるべきではないと考えています。その真価は、スコアの背景にある顧客の行動履歴を読み解き、営業とマーケティングの対話を深めるきっかけとすることにあります。
高スコアのリードを営業へ引き渡す際、「この方は3日前に料金ページを閲覧し、昨日、A社の導入事例をダウンロードしている」といった具体的な行動履歴を共有する。この一言が、営業担当者のアプローチの質を変えます。営業は、顧客の興味関心を事前に把握した上で、「A社の事例にご関心をお持ちいただきありがとうございます。特にどのような点に課題を感じていらっしゃいますか?」といった、核心に迫る対話からスタートできるのです。
スコアは、顧客をより深く理解し、部門を超えてその理解を共有するための共通言語です。この視点を持つことで、スコアリングは単なる効率化ツールから、顧客体験を向上させる戦略的な武器へと進化します。
MAで完結させない。SFA/CRM連携で実現するマーケティングROIの可視化
SATORIのスコアリングの価値を最大化するためには、MAツール内で完結させず、SFA(営業支援システム)やCRM(顧客管理システム)と連携させることが不可欠です。
SATORIで算出したスコアや行動履歴をSFA/CRMに連携させることで、営業担当者は普段使っているツール上で、顧客の最新の興味関心を確認しながら活動できます。
さらに重要なのは、その逆、つまりSFA/CRM上の商談結果(受注・失注、受注金額など)のデータをMAにフィードバックさせることです。これにより、「どのマーケティング施策(高スコアの源泉)が、最終的に最も大きな売上に繋がったのか」という、マーケティング活動のROI(投資対効果)を明確に可視化できるようになります。
このデータに基づいた分析は、スコアリングの精度をさらに高めるだけでなく、マーケティング部門が自部門の活動価値を経営層に定量的に示すための、非常に重要なデータとなるでしょう。
主要MAツールとのスコアリング機能比較
HubSpot、Marketoとの機能・思想の違いを客観的に分析
SATORIのスコアリング機能を検討する上で、他の主要なMAツールとの違いを理解しておくことは有益です。
比較項目 | SATORI | HubSpot | Marketo (Adobe) |
|---|---|---|---|
| スコアリングの基本思想 | 行動ベースが中心。匿名リードへのスコアリングにも対応し、日本の商習慣にフィットしやすい。 | CRMが全ての中心。顧客情報全体を統合的に評価する思想が強い。 | 大規模で複雑なルール設定に対応可能。ABM(アカウントベースドマーケティング)戦略との親和性が高い。 |
| 設定の容易さ | 直感的な日本語UIで、比較的容易に始められる。 | ガイド機能が充実しており、初心者でも設定しやすい。 | 高度な設定が可能な分、学習コストが高く、専門知識を要する傾向がある。 |
最適な企業像 | 日本国内の中小〜中堅企業。初めてMAを導入し、営業連携を重視する企業。 | スタートアップから中堅企業まで幅広く対応。インバウンドマーケティングを主軸とする企業。 | マーケティング組織が成熟した中堅〜大企業。グローバルで複雑な施策を展開する企業。 |
なぜ日本のBtoB企業にSATORIがフィットしやすいのか
日本のBtoB企業では、営業現場の細やかなフォローや、匿名リードも含めた幅広いアプローチが求められます。SATORIは、こうした現場のニーズに応えるため、
- 匿名リード管理やセグメントごとのスコアリング
- 日本語でのサポートや導入支援
- 営業部門との連携を前提とした柔軟な設定
といった機能・体制を整えています。
特に営業部門との密な連携や、現場のフィードバックを反映したスコア設計を重視する企業にとって、SATORIは「使いこなせるMAツール」として高い評価を得ています。
まとめ:SATORIスコアリングを成功に導く、はじめの一歩
本記事では、SATORIのスコアリング機能を最大限に活用し、ビジネスの成果に繋げるための考え方と具体的な手法を解説しました。
スコアリングは、単にリードを点数付けする作業ではありません。それは、営業とマーケティングが顧客という同じ目標に向かうための「共通言語」であり、データに基づいて対話し、連携を深めるための重要な仕組みです。
成功のポイントを改めて整理します。
何よりも先に、営業部門と「ホットリード」の定義を徹底的にすり合わせること。
シンプルな設定から始め、PDCAサイクルを回しながら継続的に改善していくこと。
スコアを「対話のきっかけ」と捉え、顧客理解を深めるために活用すること。
SFA/CRMと連携させ、マーケティング活動の成果を可視化すること。
まずは過去の受注データに目を向けることから始めてみてください。直近で成約に至った優良顧客が、商談前にどのような行動を取っていたか。その事実に基づいたデータは、営業部門と「ホットリード」の定義をすり合わせる上で、何より説得力のある材料となります。
MAツールの導入・活用の相談はSells upへ。
MAツールの導入や、導入後の成果最大化に課題をお持ちでしたら、ぜひSells upにご相談ください。50社以上の導入・活用を支援してきた担当者が貴社の状況・目標に向き合い、最適なツールの導入プラン / 統計知識を用いた活用プラン描き、戦略策定から実装 / 実行 / 効果測定までをご支援いたします。
CONTACT







