リードナーチャリングとは?意味から手法、成功のポイントまでをBtoBのプロが解説
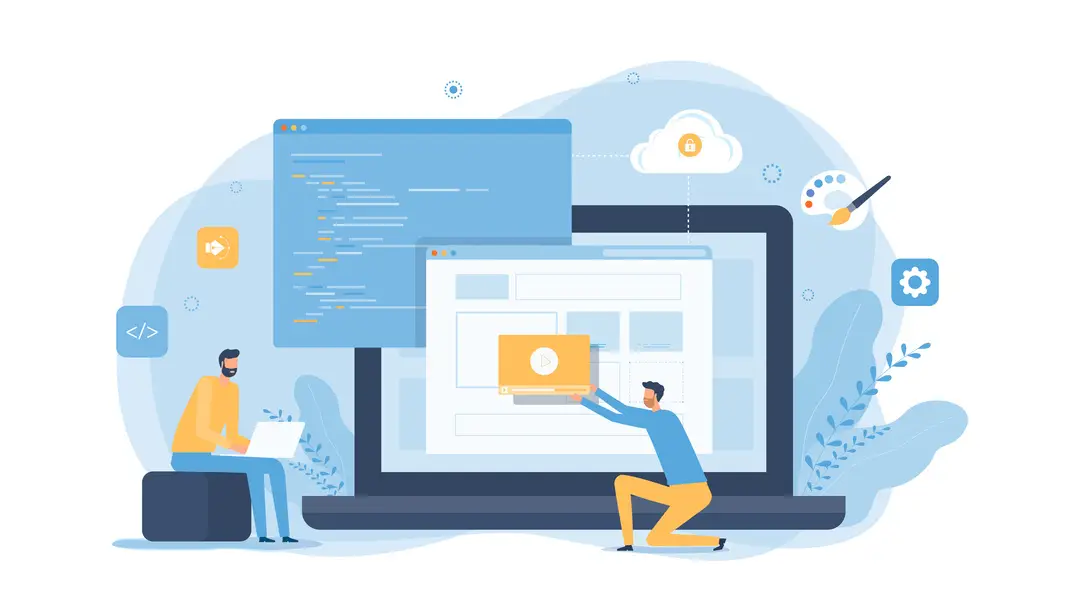
MAツールの導入・活用の相談はSells upへ。
MAツールの導入や、導入後の成果最大化に課題をお持ちでしたら、ぜひSells upにご相談ください。50社以上の導入・活用を支援してきた担当者が貴社の状況・目標に向き合い、最適なツールの導入プラン / 統計知識を用いた活用プラン描き、戦略策定から実装 / 実行 / 効果測定までをご支援いたします。
リードナーチャリングとは? BtoBマーケティングで重要視される理由
BtoBマーケティングでは、リードナーチャリングがこれまで以上に注目されています。
「毎月一定数のリードは獲得できているのに、なかなか商談につながらない」
「営業部門から『まだ温度感が低い』『もっと質の高いリードが欲しい』と指摘される」
「獲得したリードの多くがフォローされないまま休眠化している」
もし貴社がこのような課題を抱えているなら、その解決策はリードナーチャリングにあるかもしれません。
営業活動や商談獲得の難易度が高まる一方で、獲得した見込み顧客(リード)の多くが有効活用されていない現実があります。特に、リード獲得後のプロセスに課題を感じているマーケティング担当者の方は多いのではないでしょうか。
リードナーチャリングは、単にリード数を追うだけのアプローチではなく、リード一人ひとりの関心度や検討段階に合わせてアプローチし、購買意欲を高めるための一連の活動です。営業リソースの最適化や、マーケティング活動のROI向上にも直結するため、今やBtoBビジネスの成長を左右する重要な要素となっています。
本記事では、リードナーチャリングの基本的な定義から、具体的な手法、導入手順、そして多くの企業が直面する「営業連携の壁」を乗り越えるためのポイントまでを網羅的に解説します。
リードナーチャリングの基本的な意味:「見込み顧客の育成」
リードナーチャリング(Lead Nurturing)とは、文字通り「見込み顧客(リード)を育成する」ことを指します。ここでいう「育成」とは、単に情報提供を続けるだけではありません。リードが自社の商品やサービスに対する理解を深め、購買意欲を高めていくよう、段階的に働きかけるプロセス全体を指します。
例えば、展示会やWeb広告で獲得したリードは、すぐに購買行動に移るとは限りません。多くの場合、情報収集や比較検討の段階にあり、営業担当者がアプローチしても「まだ検討中」「情報収集段階なので」と断られてしまうこともあります。
リードナーチャリングは、こうしたリードの検討フェーズや関心度に合わせて、メールやコンテンツ、セミナーなどを活用し、徐々に購買に近づけていくための活動です。
デマンドジェネレーションにおける位置づけ:3つのプロセスの関係性
BtoBマーケティングの全体像を理解するうえで欠かせないのが、「デマンドジェネレーション」の考え方です。デマンドジェネレーションは、見込み顧客の獲得から商談・受注までの一連のプロセスを体系的に整理したもので、主に以下の3つの段階に分けられます。
リードジェネレーション(見込み顧客の獲得)
リードジェネレーションは、Web広告や展示会、オウンドメディア、SNSなどを活用して、見込み顧客の情報を獲得する活動です。マーケティング活動の出発点となりますが、ここで集めたリードは、購買意欲や検討段階に大きなバラつきがあります。
リードナーチャリング(見込み顧客の育成)
リードナーチャリングは、獲得したリードの関心度や検討フェーズに合わせて、段階的に情報提供やコミュニケーションを行うことで、購買意欲を高める活動です。ここでの「育成」が不十分だと、せっかくのリードが休眠状態になり、営業活動の効率も低下します。
リードクオリフィケーション(見込み顧客の選別)
リードクオリフィケーションは、ナーチャリングによって育成されたリードの中から、受注可能性が高い「ホットリード」を選別し、営業部門に引き渡すプロセスです。スコアリング(後述)や行動履歴をもとに、商談化の確度が高いリードを抽出します。
なぜリードナーチャリングが重要なのか? 3つの背景
なぜ今、リードナーチャリングに取り組む必要があるのでしょうか。その背景には、BtoB領域特有の購買行動の変化があります。
背景1:購買プロセスの長期化・複雑化への対応
BtoB領域では、意思決定プロセスが長期化・複雑化しています。インターネットの普及により、顧客は営業担当者に会う前に、Webサイトなどで多くの情報を収集できるようになりました。複数の担当者や決裁者が関与し、比較検討に多くの時間が割かれるため、リード獲得から商談・受注までに半年から1年以上かかるケースも珍しくありません。こうした状況下では、リードナーチャリングによる継続的な関係構築が不可欠です。
背景2:営業リソースの最適化と効率向上
営業部門がすべてのリードにアプローチするのは効率的ではありません。特に、まだ情報収集段階にあるリードに対して早期にアプローチしても、空振りに終わる可能性が高くなります。ナーチャリングを通じて購買意欲が高まったリードを営業に引き渡すことで、営業リソースを確度の高いリードに集中できます。これにより、商談化率や受注率の向上が期待できます。
背景3:獲得したリード資産の価値を引き出す
広告費や展示会出展などでコストをかけて獲得したリードを放置してしまうと、せっかくの投資が無駄になってしまいます。また、時間の経過とともにリード情報の有効性が低下する可能性もあります。リードナーチャリングは、獲得したリードを「資産」として捉え、その価値を引き出すための取り組みです。休眠リードの掘り起こしや、再アプローチによる商談化にもつながります。
【Sells upの視点】リードナーチャリングの本質は「顧客理解の深化」
リードナーチャリングは、単なる営業効率化やリードの掘り起こしだけを目的とするものではありません。Sells upでは、リードナーチャリングの本質を「顧客理解を深めるプロセス」と捉えています。
リードがどのようなコンテンツに反応し、どのような経路で情報収集を行っているかを分析することで、顧客が抱える真の課題やニーズが鮮明になります。このプロセスを通じて得られた示唆は、マーケティング施策の改善だけでなく、営業トークの洗練や、時には製品開発へのフィードバックにも活用できます。
つまり、リードナーチャリングに正しく取り組むことは、企業全体の顧客中心主義を推進することにつながります。目先の商談数だけでなく、中長期的な視点で顧客との関係性を構築することが重要です。
リードナーチャリングの具体的な手法5選【目的別】
リードナーチャリングにはさまざまな手法がありますが、ここではBtoBマーケティングで効果的な5つの手法を目的別に解説します。重要なのは、これらの手法を顧客の状況に合わせて組み合わせることです。
手法1:メールマーケティング|基本にして重要なチャネル
メールは、リードナーチャリングの中核を担うチャネルです。コスト効率が高く、パーソナライズや自動化も容易なため、多くの企業で活用されています。
ステップメール/シナリオメール
リードの行動や関心度に合わせて、段階的にメールを配信する手法です。例えば、資料ダウンロード後に自動でお礼メールを送り、その後製品の活用事例や導入事例を順に案内するなど、リードの検討フェーズを少しずつ進めていくことができます。
メールマガジン
定期的に情報提供を行うことで、リードとの接点を維持し続ける役割を果たします。業界トレンドやノウハウ、成功事例など、リードにとって価値ある情報を届けることが重要です。一斉配信だけでなく、特定の条件で分類したリードに送る「セグメントメール」も有効です。
手法2:オウンドメディア・Webコンテンツ|顧客自らが学ぶ場を提供する
自社で運営するオウンドメディアやWebコンテンツは、リードが自ら情報収集・学習できる場を提供します。
ブログ記事
業界の最新動向や課題解決のヒント、製品の使い方など、幅広いテーマでリードの興味を引きつけます。SEO対策を施すことで、新規リードの獲得にもつながります。
ホワイトペーパー・お役立ち資料
リードが抱える課題に対して、体系的な解決策やノウハウをまとめた資料を提供します。ダウンロード時にリード情報を取得できるため、リードジェネレーションとナーチャリングの双方で活用できます。
手法3:セミナー・ウェビナー|購買意欲を大きく引き上げる機会
セミナーやウェビナーは、リードの購買意欲を一気に高める有効な手段です。直接対話ができるため、リードの疑問や不安をその場で解消し、商談化への後押しが可能です。オンライン開催であれば、地理的な制約なく多くのリードを集客できます。
手法4:リターゲティング広告|接点を持ち続けるための補完策
一度自社サイトを訪れたリードに対して、Web広告を通じて再度アプローチする手法です。検討段階で離脱したリードに対し、再訪問や資料請求を促すことで、商談化の機会を増やします。メールなど他のチャネルと組み合わせることで、多角的に接点を維持できます。
手法5:インサイドセールスによる個別アプローチ|「人」による育成
電話やメール、オンラインミーティングなどを通じて、リード一人ひとりの状況に合わせた個別フォローを行う手法です。特に検討度の高いリードや、意思決定者が複数いる場合に有効です。マーケティング部門と営業部門の連携役としても重要な役割を担います。
【Sells upの視点】何から始めるべきか?リソースに応じた段階的導入
多くの手法を前にして、「何から手をつければ良いのか分からない」と感じる方も多いでしょう。特にリソースが限られる場合、全手法を同時に展開するのは現実的ではありません。Sells upでは、自社の成熟度に合わせて段階的に導入することを推奨しています。
まずは手動運用とメールから
まずは「メールマーケティング」から着手します。Excel管理でも構いませんので、既存のリストに対して定期的な情報提供(メルマガ)を行います。メールはコストが低く、成果を可視化しやすいため、限られたリソースでも運用が可能です。目的は、リードとの接点を維持し、基本的なPDCAを回す習慣をつけることです。
コンテンツ充実とセグメンテーション
次に、オウンドメディアやホワイトペーパーの充実を図り、リードが自ら情報収集できる環境を整えます。同時に、顧客セグメンテーション(業種別、課題別など)を精緻化し、部分的な自動化(ステップメールなど)に取り組み始めます。
MAツール導入と施策の高度化
体制が整ってきたら、MA(マーケティングオートメーション)ツールを本格的に導入し、自動化・パーソナライズを進めます。スコアリングによるホットリードの自動抽出や、セミナー、インサイドセールスなど、リードの検討度合いに応じた高度な施策を連携させていきます。
貴社の現状(リード量、営業体制、コンテンツリソース)を正しく把握し、無理なく継続できる運用体制を構築することが、リードナーチャリングの成果につながります。
リードナーチャリングの始め方|成果を出すための5つのステップ
リードナーチャリングを効果的に進めるには、やみくもに施策を打つのではなく、体系立てたプロセスに沿って進めることが重要です。ここでは、成果につなげるための5つのステップを解説します。
Step.1:顧客の定義と分類(セグメンテーション)
まずは、ターゲットとなる顧客像を明確にし、リードを適切に分類します。
ターゲット顧客の解像度を高める(ペルソナ設定)
年齢、業種、職種、役職、課題意識、意思決定プロセスなど、貴社にとって価値の高い顧客像(ペルソナ)を具体的に設定してください。曖昧なターゲット設定では、施策の精度が大きく低下します。
顧客の検討フェーズを定義する
「認知」「興味・関心」「比較・検討」「意思決定」など、顧客の検討段階を可視化し、各リードが現在どのフェーズにいるのかを把握します。これにより、最適な情報提供やアプローチ方法が選択できるようになります。
Step.2:カスタマージャーニーの設計
次に、ターゲット顧客がどのようなプロセスを経て購買に至るのかを整理します。
各フェーズでの顧客の課題と必要な情報を整理する
顧客が各検討フェーズで「何を考え」「どのような行動を取り」「どのような情報を求めているか」を具体的に描き出します。例えば、「認知」フェーズでは業界トレンドや課題提起、「比較・検討」フェーズでは製品の導入事例や価格情報などが求められます。ジャーニーマップを作成し、顧客視点で必要な接点とコンテンツを明確にしましょう。
Step.3:コンテンツのマッピングと設計
カスタマージャーニーの各段階に合わせて、どのようなコンテンツを用意するかを決めます。リードナーチャリングは「何を届けるか」が成否を分けます。
ジャーニーの各段階に合わせたコンテンツ設計の具体例
顧客の検討フェーズごとに有効なコンテンツは異なります。以下のようにマッピングして、コンテンツ戦略とナーチャリング施策を連動させましょう。
認知・興味関心層向け:
目的:課題の明確化、解決策の提示
例:ブログ記事、業界動向レポート、ノウハウ系ホワイトペーパー
比較・検討層向け:
目的:自社製品の優位性理解、導入後のイメージ醸成
例:導入事例集、製品比較資料、FAQ、製品紹介ウェビナー
意思決定層向け:
目的:導入への不安払拭、意思決定の後押し
例:無料トライアル、ROI試算シート、個別相談会
【Sells upの視点】リードナーチャリングにおけるコンテンツ設計の思想
リードナーチャリングを成功させるためには、単にコンテンツの量を増やすのではなく、「顧客の検討フェーズを前に進める」という視点でコンテンツを設計することが重要です。
多くの企業が陥りがちな失敗は、自社が伝えたい情報(製品の機能やメリット)を一方的に提供してしまうことです。しかし、リードが求めているのは「自分の課題を解決するための情報」です。
Sells upでは、以下の3つの視点を重視してコンテンツ設計を行うことを推奨しています。
課題起点: 顧客が抱えるビジネス課題を起点とし、その解決策として自社製品を位置づける。
フェーズ適合性: 検討フェーズごとに異なる顧客の疑問や不安に的確に応える内容にする。
ネクストアクションの明示: コンテンツを読んだ後、次に取るべき行動(関連資料のダウンロード、セミナーへの参加など)を明確に示し、自然な流れで次のフェーズへ誘導する。
この設計思想を持つことで、コンテンツがナーチャリング施策の中で機能し、より高い成果を生み出すことが可能になります。
Step.4:シナリオの設計と施策の実行
「誰に」「何を」「いつ」「どのチャネルで」届けるかを具体的に設計し、施策を実行します。
どのセグメントのリードに
どのタイミングで
どのコンテンツやチャネルを使い
どのようなアプローチをするか
を明確にし、メール配信やウェビナー案内、インサイドセールスによるフォローなど、複数の施策を組み合わせて展開します。例えば、「資料Aをダウンロードしたリードには、3日後に事例Bをメールで案内し、そのメールを開封したらインサイドセールスがフォローコールする」といった流れを設計します。
Step.5:効果測定と改善(PDCA)
施策を実施したら、必ず効果測定を行い、改善を繰り返してください。
設定すべきKPIと評価方法
事前にKPIを設定し、定期的にモニタリングします。
メール開封率・クリック率
ホワイトペーパーダウンロード数
セミナー参加率
商談化率・受注率
営業へのリード引き渡し数(MQL創出数)
など、KPIを事前に設定し、定期的にモニタリングします。成果が思わしくない場合は、コンテンツやシナリオ、ターゲット設定を見直し、PDCAサイクルを回していくことが重要です。
リードナーチャリング成功の3つの重要ポイント
成果を出すために押さえておきたい、リードナーチャリングの重要ポイントを3つ紹介します。これらは多くの企業がつまずきやすい点です。
ポイント1:リードスコアリングの設計と運用
スコアリングとは何か?
リードスコアリングは、リードの行動や属性に点数を付け、商談化の確度(ホット度合い)を数値で可視化する仕組みです。例えば、「メール開封で3点」「資料ダウンロードで10点」「ウェビナー参加で20点」「料金ページ閲覧で15点」など、リードのアクションごとにスコアを設定します。これにより、客観的な基準でリードを選別(クオリフィケーション)できるようになります。
シンプルに始めるスコアリング設定のコツ
初めから複雑なスコアリングを設計する必要はありません。まずは主要なアクションに限定して点数を割り振り、一定のスコアを超えたリードを営業部門に引き渡す運用から始めましょう。重要なのは、運用しながら実際の商談化率や受注率をもとに、スコアの配点基準を継続的に見直していくことです。
ポイント2:MA(マーケティングオートメーション)ツールの活用
MAツールで何ができるのか?
MAツールを活用すると、リード情報の一元管理、メール配信の自動化、ウェブ行動のトラッキング、スコアリング、シナリオ設計などが可能になります。人手では追いきれない細かなアプローチや、複数チャネルの連携も効率化でき、リードナーチャリングの精度と効率が向上します。
【Sells upの視点】「戦略が先、ツールは後」の原則を忘れない
MAツールは高機能ですが、「導入すれば成果が出る」ものではありません。多くの企業がMAツール導入で失敗する原因は、「ツールありき」で検討を進めてしまい、その前段階で固めるべき戦略が欠如していることにあります。
Sells upが重要視するのは、「戦略が先、ツールは後」という原理原則です。MAツールを導入する前に、以下の要素が固まっている必要があります。
誰に(ペルソナ): ターゲット顧客は誰か?
どのような経験を提供するか(カスタマージャーニー): 顧客はどのようなプロセスで購買に至るか?
そのためにどんな情報が必要か(コンテンツ): 各プロセスでどのようなコンテンツが必要か?
どのように運用するか(運用体制とKPI): 誰が担当し、何を目標とするか?
これらの戦略設計が不十分なままツールを導入しても、運用が回らず、高価なツールを有効活用できない状況に陥ります。ツール導入を成功させるためには、まず自社のマーケティング戦略を明確にすることが不可欠です。
ポイント3:マーケティングと営業の連携強化
リードナーチャリングの最終的な目的は売上への貢献です。そのためには、マーケティング部門と営業部門の連携が不可欠です。部門間の断絶は、多くの企業が抱える根本的な課題であり、連携の強化はリードナーチャリングの成否を分ける重要なポイントです。
リードの質の定義を部門間ですり合わせる(MQLの定義)
マーケティング部門が「有望だ」と判断して渡したリード(MQL:Marketing Qualified Lead)を、営業部門がフォローしない、あるいは営業から「リードの質が低い」と指摘されるケースは少なくありません。
この問題を解決するには、両部門で「どのような状態のリードを営業に引き渡すか」という基準(MQLの定義)を明確にし、共通認識を持つ必要があります。例えば、「スコアが○点以上」「ウェビナー参加後に資料請求したリード」など、定量的・定性的な基準を共有することで、部門間の齟齬を防げます。
引き渡しルールを明確化する(SLA)
部門間の連携を口約束で終わらせず、仕組み化するためには、SLA(Service Level Agreement)の締結が有効です。SLAとは、部門間で合意した役割分担や対応ルールを定めたものです。
マーケティングの責任例: 月間〇件のMQLを創出する。
営業の責任例: MQLを受け取ったら、〇営業日以内に必ずアプローチし、結果を入力する。
このようにルールを明確化することで、リードの取りこぼしを防ぎ、建設的な議論が可能になります。
フィードバックループの構築
マーケティング部門は、引き渡したリードがその後どうなったのか(商談化したか、失注した場合の理由は何か)を把握する必要があります。営業からのフィードバックがなければ、施策の評価や改善ができません。「月1回の合同ミーティング」「SFAのダッシュボード共有」「商談の振り返り」など、営業からのフィードバックが定期的にされるように組み込みましょう。
【Sells upの視点】成功の分かれ道は「組織の壁を越える仕組み」にある
Sells upが現場で数多く見てきた成功企業の共通点は、単にツールや手法を導入しているだけでなく、マーケティングと営業が組織の壁を越える「仕組み」を持っている点にあります。
多くの記事では「質の高いリードを営業に渡す」という理想論が語られますが、現場で本当に必要なのは、MQLの定義、SLAの締結、フィードバックループの構築といった具体的なプロセスです。
特に、部門間の連携を進める上で、以下の具体的なアクションを推奨しています。
月1回の合同ミーティングの実施:KPIの進捗共有だけでなく、具体的なリードに対する評価や改善策を議論する場を設けます。
商談化したリードの振り返り:なぜ商談化したのか、その要因を分析し、成功パターンを共有します。
失注理由の共有と分析:なぜ失注したのか、その理由をマーケティング部門にフィードバックし、コンテンツやシナリオの改善に活かします。
貴社でも、まずはこうしたシンプルな仕組みづくりからスタートすることが、リードナーチャリングの成果を大きく左右します。
リードナーチャリングの成功事例
リードナーチャリングは、理論やフレームワークだけでなく、実際の現場で成果につなげた事例から学ぶことが重要です。ここでは、BtoB企業でよくある3つのシーンごとに、具体的な取り組みと成果を紹介します。
事例1:休眠リードの掘り起こしによる商談創出(BtoB SaaS)
あるSaaS企業では、過去に資料請求やセミナー参加履歴のあるものの、1年以上商談化していなかったリードが大量に存在していました。そこで、MAツールを活用し、休眠リードに対して新サービスの案内メールと限定セミナーの招待を実施。メール開封やセミナー参加などのアクションを起こしたリードをインサイドセールスが優先フォローする体制を構築しました。その結果、約3か月で商談数が従来比1.5倍に増加し、休眠リードからの成約も複数生まれました。
事例2:ウェビナー参加者へのフォローで受注率を改善(ITソリューション)
ITソリューションを提供する企業では、ウェビナーの集客には成功していたものの、参加後の商談化率が伸び悩んでいました。そこで、参加者のアンケート回答やチャットでの質問内容をもとに、関心度の高いリードを抽出。ウェビナー終了直後にインサイドセールスが個別フォローを行い、具体的な課題ヒアリングや個別デモの提案を実施しました。その結果、ウェビナー経由の受注率が従来の2倍以上に向上しました。
事例3:コンテンツの出し分けで顧客単価を向上(製造業)
製造業のBtoB企業では、見込み顧客の業種や役職によって関心テーマが異なることが課題でした。そこで、MAツールのセグメント機能を活用し、業種別・役職別に最適化したホワイトペーパーや事例集をメールで配信。さらに、ダウンロード履歴やWeb閲覧履歴に応じて、次に送るコンテンツも自動で出し分ける設計にしました。これにより、商談時に顧客の課題理解が深まり、アップセルやクロスセルの提案がしやすくなり、結果として顧客単価が20%以上向上しました。
まとめ:リードナーチャリングは売上を継続的に生み出す仕組みづくり
リードナーチャリングは、単なるリードへの情報提供ではありません。見込み顧客の検討段階や課題に合わせて、最適なタイミングと方法でアプローチし続ける「仕組み」です。
BtoBの購買プロセスが長期化・複雑化する中で、リードを「資産」として活用し続けることが、持続的な売上成長のポイントとなります。そして、その仕組みを機能させるためには、顧客理解に基づくコンテンツ設計という「中身」と、マーケティング部門と営業部門の連携という「体制」の両輪が重要です。
本記事で紹介した手法や成功のポイント、プロセスを参考に、貴社でもリードナーチャリングの仕組みづくりに着手してください。まずは自社のリソースに合わせ、メールやコンテンツの充実、営業との小さな連携から始め、PDCAを回しながら取り組みを深化させていくことが、商談化率・受注率の改善への近道です。
MAツールの導入・活用の相談はSells upへ。
MAツールの導入や、導入後の成果最大化に課題をお持ちでしたら、ぜひSells upにご相談ください。50社以上の導入・活用を支援してきた担当者が貴社の状況・目標に向き合い、最適なツールの導入プラン / 統計知識を用いた活用プラン描き、戦略策定から実装 / 実行 / 効果測定までをご支援いたします。
CONTACT







