ナーチャリングコンテンツとは?BtoBで成果を出す「運用サイクル」と作成手順を解説
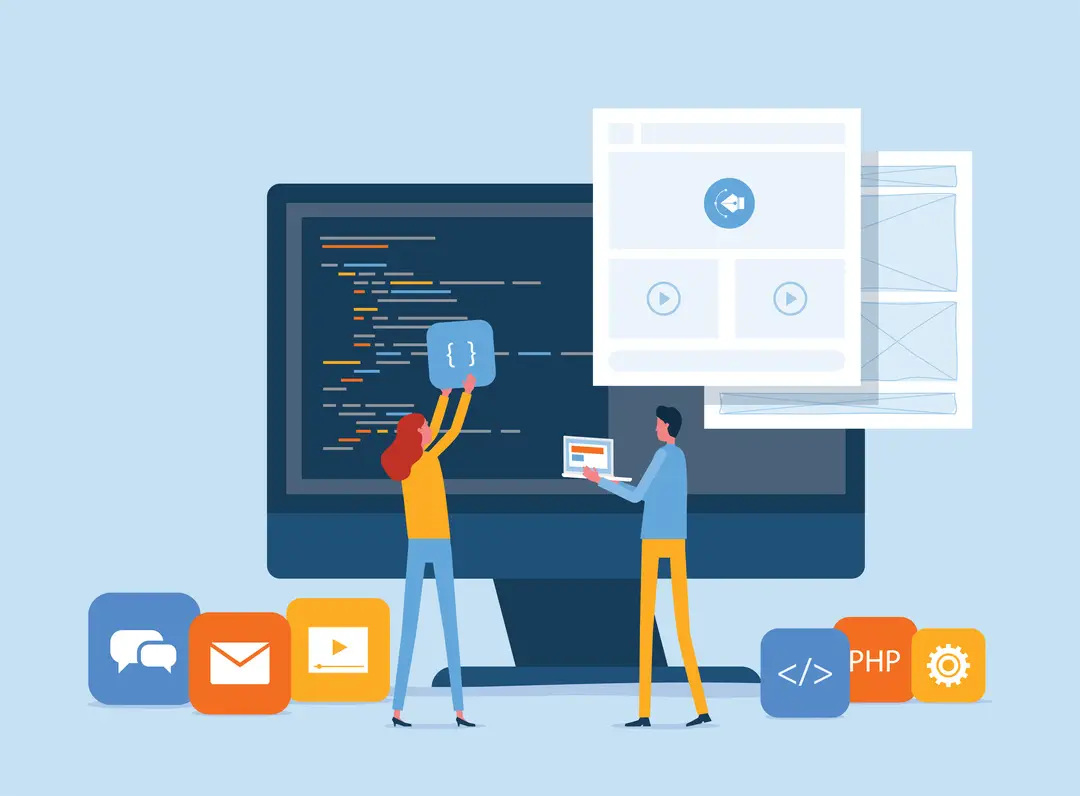
MAツールの導入・活用の相談はSells upへ。
MAツールの導入や、導入後の成果最大化に課題をお持ちでしたら、ぜひSells upにご相談ください。50社以上の導入・活用を支援してきた担当者が貴社の状況・目標に向き合い、最適なツールの導入プラン / 統計知識を用いた活用プラン描き、戦略策定から実装 / 実行 / 効果測定までをご支援いたします。
BtoBマーケティングにおいて、リード獲得後の商談化率が低迷するケースは少なくありません。
その多くは、コンテンツ施策が担当者の思いつきや単発の活動になってしまい、成果(商談創出)に繋がる体系的なナーチャリングコンテンツ運用の仕組みが構築できていないことに起因します。
本記事では、「思いつきの施策ではなく、成果に繋がる、体系的で継続可能なナーチャリングコンテンツ運用を自社で確立する」ための、具体的なプロセスと仕組みの全体像、その確立手順について詳しく解説します。
成果(商談創出)に繋がる「ナーチャリングコンテンツ運用サイクル」の全体像
ナーチャリングコンテンツ運用の目的は、マーケティング活動のROI(投資対効果)を高め、最終的に商談を創出することです。そのためには、コンテンツを「作って終わり」にするのではなく、戦略設計から効果測定、改善、そして営業部門との連携までを一貫した「運用サイクル」として捉え、継続的に回していく必要があります。
思いつきの施策から脱却するための5つのステップ
体系的な運用を実現するための「ナーチャリングコンテンツ運用サイクル」は、以下の5つのステップで構成されます。
Step.1:戦略設計(顧客理解と目標設定)
ペルソナとカスタマージャーニーを明確にし、運用全体の目標(KPI)を設定します。
Step.2:コンテンツ企画とマップ作成
Step.1の戦略に基づき、各検討フェーズで必要なコンテンツを洗い出し、全体像(コンテンツマップ)を作成します。
Step.3:コンテンツ制作と配信設定
具体的なコンテンツを制作し、MA(マーケティングオートメーション)ツールなどを活用して、顧客の状況に合わせて届ける仕組み(シナリオなど)を設計します。
Step.4:効果測定とデータ分析
配信結果をデータで分析し、どのコンテンツが商談化に貢献しているかを測定・可視化します。
Step.5:改善と営業連携
分析結果に基づき、コンテンツやシナリオを改善します。また、確度の高まったリードを営業部門へスムーズに引き渡し、連携体制を強化します。
この5つのステップを継続的に回す仕組みを構築することが、思い付きの運用から脱却し、成果を向上させるための道筋となります。
【徹底解説】ナーチャリングコンテンツ運用サイクルの確立手順
ここでは、運用サイクルを回し、商談創出に直結させるための具体的な手順を解説します。
Step.1:戦略設計(顧客理解と目標設定)
運用サイクルの基盤となるのは、ターゲット顧客に対する深い理解と、それに基づく戦略設計です。
ペルソナとカスタマージャーニーの明確化
まず、「誰に・何を・どのように届けるか」を明確にするため、以下の作業を行います。
ペルソナ設定:ターゲットとなる顧客の具体的な属性(業種、役職、抱える課題、情報収集の方法、意思決定プロセスなど)を定義します。営業部門へのヒアリングや既存顧客の分析が有効です。
カスタマージャーニーの可視化:ペルソナが自社の製品・サービスを認知してから、情報収集、比較検討を経て、意思決定に至るまでの思考や行動プロセスを整理します。各段階でどのような情報を求めているかを洗い出します。
ビジネス成果に直結するKPIの設定
次に、運用全体の目標を数値で設定します。ここで重要なのは、メールの開封率やクリック率といった中間指標だけではなく、ビジネス成果への貢献度を測るKPIを設定することです。
最終目標(KGI):コンテンツ経由の商談創出数、受注数、パイプライン金額など。
中間目標(KPI):商談化率、ホットリード(購買意欲の高い見込み顧客)創出数、特定コンテンツのダウンロード数など。
これらのKPIを設定することで、施策の評価基準が明確になり、改善サイクルを回しやすくなります。
【Sells upの視点】KPI設定は「計測できること」から始める
理想的なKPIは「コンテンツ単位での商談貢献度」ですが、MAツールやSFA(営業支援システム)の連携が不十分な場合、これを正確に計測するのは難しい場合があります。KPIを設定しても計測できなければ、運用は改善されません。
Sells upでは、まずは現状のデータ環境で「計測できる指標」からKPIを設定し、運用を回し始めることを推奨しています。例えば、まずは「導入事例集をダウンロードしたリードのその後の商談化率」など、限定的な範囲から計測を開始します。そして、運用を回しながら徐々に計測環境を整備し、理想のKPI管理へと近づけていくアプローチが現実的です。
Step.2:コンテンツ企画とマップ作成
Step.1で明確にしたペルソナとカスタマージャーニーに基づき、具体的にどのようなコンテンツが必要かを企画し、全体像を整理します。
コンテンツマップの作成と棚卸し
カスタマージャーニーの各フェーズで必要となるコンテンツテーマを洗い出し、「コンテンツマップ」を作成します。
コンテンツテーマの洗い出し:ペルソナの課題や関心事を軸に、必要なテーマを網羅的にリストアップします。
既存コンテンツの棚卸しとギャップ分析:すでに存在するコンテンツ(ブログ記事、営業資料、過去のセミナー動画など)を整理し、コンテンツマップ上で不足しているテーマや、内容が古くなっているものを特定します。
制作優先度の決定:不足しているコンテンツ(ギャップ)の中から、商談化への貢献度が高い(比較検討フェーズに近い)ものから優先的に制作計画を立てます。
営業連携を前提としたコンテンツ企画
コンテンツ企画時には、マーケティング部門だけではなく、営業部門の視点を取り入れることが重要です。「商談でよく聞かれる質問」「提案時にあると助かる資料」「顧客が導入を決めた理由」などをヒアリングし、営業活動でも活用できるコンテンツ(セールスコンテンツ)を企画します。
【Sells upの視点】「営業が使える武器」としてのコンテンツ企画
Sells upでは、ナーチャリングコンテンツを単なる情報発信ツールとしてだけではなく、「営業活動を効率化する武器」や「顧客の検討状況を測る温度計」として位置づけることが重要であると考えています。企画段階から営業部門を巻き込むことで、より成果に直結するコンテンツを作成できます。
具体的には、以下のような視点を取り入れます。
営業が直面する「よくある反論」への回答
顧客から頻繁に出る懸念点や競合比較の質問に対して、先回りして回答するコンテンツ(FAQ、比較表など)を用意します。これにより、商談の初期段階でのユーザーの離脱を防ぎます。「顧客の検討状況を測る温度計」としての活用
例えば、「料金体系の詳細資料」や「導入までのステップ解説」といった、検討度合いが高い顧客だけが関心を持つコンテンツを用意します。これらのコンテンツへの反応を検知することで、アプローチすべきホットなリードを特定できます。
このように、営業活動との連携を前提に企画することで、コンテンツの利用価値は格段に高まります。
Step.3:コンテンツ制作と配信設定
企画したテーマに基づき、コンテンツを制作し、顧客に届けるための配信設定を行います。
各コンテンツの制作のポイント
コンテンツを制作する際は、以下のポイントを押さえることが重要です。
目的と行動変容の定義:そのコンテンツを読んだ後、顧客にどのような態度変容や行動(例えば、別資料のダウンロード、問い合わせなど)を起こしてほしいかを明確にします。
顧客視点の徹底:自社が伝えたいことではなく、顧客が知りたいこと、課題解決に役立つ情報を中心に構成します。売り込み色を抑えることが信頼に繋がります。
信頼性と専門性の担保:データや導入事例、自社の知見など、根拠となる客観的な情報を盛り込みます。
分かりやすさ:専門用語の多用を避け、図解や箇条書きを活用して、読み手が理解しやすい構成を心がけます。
配信チャネルの選定とMAシナリオ設計
作成したコンテンツを、見込み顧客の検討状況に合わせて適切なタイミングで届けるための仕組みを設計します。
チャネルの選定:メール、オウンドメディア、SNS、ウェビナーなど、ターゲットやコンテンツの特性に応じて最適な配信チャネルを選定します。
MAシナリオ設計:MAツールを活用し、顧客の行動(例えば、資料ダウンロード、特定のWebページ閲覧など)をトリガー(きっかけ)に、自動的に最適なコンテンツを配信するシナリオを設計します。
Step.4:効果測定とデータ分析
運用サイクルを回すためには、配信したコンテンツの効果をデータで測定し、分析するプロセスが不可欠です。
データ分析と商談化貢献度の可視化
Step.1で設定したKPIに基づき、定期的にデータを分析します。
コンテンツ単位の分析:どのコンテンツがどれだけ閲覧され、最終的に商談化に貢献しているかを分析します。
シナリオ単位の分析:設計した配信シナリオ全体で、効果が出ているか、ボトルネック(離脱が多いポイントなど)はどこかを測定します。
MAツールとSFAを連携させることで、「どのコンテンツが起点となって商談が生まれたか」を可視化することが可能になります。
Step.5:改善と営業連携
分析結果に基づき、コンテンツや運用方法を改善し、さらに営業部門との連携を強化します。
コンテンツとシナリオの改善
効果が低かったコンテンツについては、内容やタイトル、CTAを見直します。シナリオについては、配信タイミングやコンテンツの順序を修正します。A/Bテストを用いて最適化することも有効です。
営業部門へのスムーズな引き渡し
ナーチャリングを通じて購買意欲が高まったリード(ホットリード)を特定し、最適なタイミングで営業部門(特にインサイドセールス)へ引き渡す仕組みを構築します。これを「クオリフィケーション」と呼びます。
具体的には、MAツールのスコアリング機能(顧客の行動に応じて点数を付与する機能)を活用し、一定のスコアに達したリードを自動的に営業部門へ通知する運用が一般的です。
【Sells upの視点】営業連携のポイントは「情報」と「役割分担」の明確化
マーケティングから営業へのリード引き渡しがうまくいかない(例えば、営業がフォローしてくれない、リードの質が低いと言われるなど)要因の多くは、部門間の連携不足にあります。Sells upでは、この課題を解決するために、単にリードリストを渡すのではなく、以下の2点を明確にすることが重要だと考えています。
引き渡す「情報」の定義
リードの基本情報だけではなく、「どのようなコンテンツに興味を示したか」「どのような課題を抱えていると推察されるか」といった、コンテンツ経由で得られたインサイト(洞察)を営業部門に共有します。これにより、営業担当者は的確な初回アプローチが可能になります。「役割分担」の明確化
どのような状態のリードを、どちらの部門が、どのようにフォローするのか、明確な基準とルールを定めます。例えば、「スコア100点以上はインサイドセールスが即時架電、50点〜99点はマーケティングが引き続きナーチャリング」といった具合です。
部門間で連携し、共通の目標(商談創出・受注)に向かう体制を構築することが、成果向上に繋がります。
そもそもナーチャリングコンテンツとは?BtoBで重要視される理由
ここでは、ナーチャリングコンテンツの基本的な定義と、BtoBマーケティングにおいてなぜ重要視されているのかについて整理します。
定義:見込み顧客の購買意欲を高める情報資産
ナーチャリングコンテンツとは、リード(見込み顧客)が自社の製品やサービスの導入を検討する過程において、適切なタイミングで届けられる、購買意欲を高めるための情報全般を指します。
単なる製品説明とは異なり、顧客が抱える課題の解決や、意思決定プロセスを支援することに主眼が置かれます。顧客との信頼関係を構築し、自社をパートナーとして認識してもらうための重要な情報資産と言えます。
BtoBマーケティングで重要な理由
BtoBビジネス特有の購買プロセスの変化により、ナーチャリングコンテンツの重要性は増しています。
購買プロセスの長期化と複雑化
BtoB製品・サービスは高額な場合が多く、導入の意思決定には複数の部門や役職者が関与します。そのため、検討期間は数ヶ月から年単位に及ぶことも珍しくありません。この長期にわたる検討プロセスにおいて、顧客との接点を維持し、各フェーズで必要とされる情報を届け続けるために、ナーチャリングコンテンツが不可欠です。
顧客主導の情報収集への対応
インターネットの普及により、顧客は営業担当者に接触する前に、Webサイトなどで自ら情報収集を行うようになりました。調査によれば、BtoBの購買プロセスの約6割は、営業担当者に会う前に完了しているとも言われています。
このような「顧客主導」の環境下では、顧客が自ら情報収集を行う段階で接点を持ち、有益なコンテンツを通じて自社を見つけてもらうことが、競合との差別化において重要になります。
検討フェーズ別・ナーチャリングコンテンツの種類と役割
ナーチャリングコンテンツは、見込み顧客の検討フェーズ(購買意欲の度合い)に合わせて、最適な種類を選ぶ必要があります。
認知・興味関心フェーズ:課題の認識を促す
まだ自社の製品を知らない、あるいは課題が明確になっていない層に対して、まずは課題を認識してもらい、興味を持ってもらうためのコンテンツです。
ブログ記事(ノウハウ・トレンド解説):業界の動向や、業務上の課題解決に役立つノウハウを発信します。
調査レポート・市場動向資料:客観的なデータに基づき、市場の現状や将来予測を提示し、課題意識を醸成します。
インフォグラフィック・チェックシート:複雑な情報を視覚的に分かりやすくまとめたり、現状を簡単に診断できるツールを用意したりします。
情報収集・比較検討フェーズ:解決策の理解を深める
課題が明確になり、具体的な解決策を探し始めている層に対して、自社製品がどのように課題解決に貢献できるかを理解してもらうためのコンテンツです。
ホワイトペーパー(課題解決資料):特定のテーマについて深掘りし、具体的な解決策と自社製品の優位性を提示します。
導入事例:他社がどのように課題を解決し、成果を上げたかという実例を紹介することで、導入後のイメージを具体化します。
ウェビナー(オンラインセミナー):製品デモや活用方法などを詳しく解説し、顧客の疑問にリアルタイムで答えます。
製品比較資料・選定ガイド:競合製品との違いや、自社製品を選ぶべき理由を客観的に整理します。
意思決定フェーズ:最後のひと押しとなる
導入の最終決定段階にある層に対して、不安や懸念を払拭し、購買を決断してもらうためのコンテンツです。
サービス紹介資料・料金表:具体的な機能や価格、導入条件などを明確に提示します。
FAQ(よくある質問):導入や運用に関する疑問点を解消します。
デモ動画・無料トライアル:実際の操作画面や使用感を体験してもらうことで、納得感を高めます。
ナーチャリングコンテンツの効果を高める3つの戦略
ナーチャリングコンテンツの運用サイクルを確立した上で、さらに効果(ROI)を高めるための3つの戦略を紹介します。
戦略1:コンテンツ資産のROIを高める二次利用
コンテンツ制作には時間とコストがかかります。限られたリソースで効果を出すためには、一度作成したコンテンツを様々な形式で再利用する視点が重要です。
例えば、1時間のウェビナーを実施した場合、以下のように複数のコンテンツに展開できます。
録画動画(アーカイブ配信)
要点をまとめたブログ記事(セミナーレポート)
詳細を解説したホワイトペーパー
質疑応答をまとめたFAQ
SNS投稿用の短い動画クリップや図解
このようにリパーパスを行うことで、制作工数を抑えながらコンテンツの量を拡充し、多様なチャネルで顧客との接点を増やすことができます。
【Sells upの視点】二次利用による効率的なコンテンツ資産構築
Sells upでは、コンテンツ制作の初期段階から二次利用を前提とした企画を行うことを推奨しています。例えば、ホワイトペーパーを作成する際、その構成案を基に、概要を説明するブログ記事や、メール配信用のアレンジ、営業が商談で使えるスライド資料などを同時に企画します。
このアプローチにより、個別にコンテンツを制作する場合と比較して、制作工数を削減できるだけではなく、発信するメッセージの一貫性を保つことができます。コンテンツを「点」ではなく「面」で捉え、効率的に資産を構築していくことが、継続的な運用を実現するポイントです。
戦略2:顧客に合わせたコンテンツのパーソナライズ
全ての見込み顧客に同じコンテンツを配信するのではなく、一人ひとりの状況に合わせて最適化(パーソナライズ)することで、反応率や商談化率の向上が期待できます。
属性による出し分け:業種、企業規模、役職などに応じて、関連性の高い業界事例や、役割に応じた課題解決コンテンツを出し分けます。
行動履歴に基づく最適化:過去に閲覧したWebページやダウンロードした資料の内容から、顧客の興味関心分野を特定し、関連するコンテンツをレコメンドします。
MAツールを活用することで、こうしたパーソナライズを効率的に実行できます。
戦略3:営業が商談で使える「セールスコンテンツ」の整備
ナーチャリングコンテンツは、マーケティング部門だけが使うものではありません。営業担当者が商談の場で活用できる「セールスコンテンツ」として整備することで、商談の質を高め、受注率向上に貢献します。
用途別・フェーズ別の体系化:顧客の検討状況や課題感に応じて、営業担当者が必要なコンテンツ(例えば、競合比較表、業界別事例集、提案時のFAQ集など)をすぐに見つけて使えるように体系化します。
使いやすいフォーマットへの最適化:マーケティング用の長文コンテンツを、営業が使いやすいように要点をまとめたスライド資料やトークスクリプトとして再編集します。
コンテンツを「営業が商談で使える武器」として位置づける視点が重要です。
ナーチャリングコンテンツ運用で陥りがちな失敗と解決策
ナーチャリングコンテンツの運用では、多くの企業が共通して直面しやすい課題があります。ここでは、よくある失敗例と、それらを乗り越えるための解決策を解説します。
失敗例1:コンテンツを作りっぱなしで活用されない・属人化する
コンテンツ制作が目的化してしまい、制作したものが活用されず、成果に結び付かないケースです。また、担当者の思いつきで企画が行われ、体系的な計画がない場合も、施策が属人化し、継続的な成果を生み出すことが難しくなります。
【解決策】 「運用サイクル」の考え方を導入し、企画段階から配信計画と活用シナリオ(誰が、いつ、どのように使うか)を明確に設計します。特に営業部門での活用を促進するためには、営業担当者が使いやすいフォーマット(セールスコンテンツ)で整備し、社内での共有会などを通じて活用方法を浸透させることが有効です。
失敗例2:営業部門との連携が機能せず、商談に繋がらない
マーケティング部門が育成したリードを営業部門に渡しても、その後のフォローが適切に行われなかったり、「リードの質が低い」という理由で放置されたりするケースです。部門間の目標や評価基準が異なり、連携がうまくいっていないことが原因です。
【解決策】 マーケティングと営業で共通の目標(例えば、商談化数や受注額)を設定し、どのような状態のリードを営業に渡すかの基準(ホットリードの定義)を明確にします。MAツールのスコアリング機能を活用し、客観的な基準でリードを評価する仕組み(クオリフィケーション)を導入することが有効です。また、定期的な情報共有会を実施し、お互いの状況や課題を理解し合う場を設けることが重要です。
失敗例3:効果測定ができず、ROI(投資対効果)を説明できない
どのコンテンツが商談化に貢献しているのかをデータで追えておらず、施策の評価や改善が感覚的に行われているケースです。これにより、経営層や他部門に対してマーケティング活動のROIを明確に説明できず、適切な投資判断が難しくなります。
【解決策】 ビジネス成果に直結するKPI(商談化率、パイプライン貢献度など)を設定し、MAツールやSFAを連携させて、データ計測基盤を構築します。コンテンツごとの貢献度を可視化し、定期的にデータをもとにした振り返りを行い、改善サイクルを回す体制を定着させることが不可欠です。
まとめ:ナーチャリングコンテンツ運用は、成果に繋がる「仕組み」作り
BtoBマーケティングにおけるナーチャリングコンテンツは、単なる情報発信ではなく、顧客との信頼関係を築き、購買意欲を段階的に高めるための重要な手段です。場当たり的な施策から脱却し、体系的かつ継続的に成果(商談創出)につなげるためには、以下のポイントが不可欠です。
ペルソナとカスタマージャーニーを起点とした戦略設計
企画から制作、配信、効果測定、改善、営業連携まで一貫した「運用サイクル」の確立
ビジネス成果に直結するKPI設定とデータドリブンな運用
営業との連携(クオリフィケーション、セールスコンテンツ整備)の強化
リパーパスやパーソナライズによる効率的なコンテンツ資産構築
ぜひ本記事で解説した「運用サイクル」を参考に、貴社でも成果に繋がるナーチャリングコンテンツ運用の仕組みづくりに取り組んでください。
MAツールの導入・活用の相談はSells upへ。
MAツールの導入や、導入後の成果最大化に課題をお持ちでしたら、ぜひSells upにご相談ください。50社以上の導入・活用を支援してきた担当者が貴社の状況・目標に向き合い、最適なツールの導入プラン / 統計知識を用いた活用プラン描き、戦略策定から実装 / 実行 / 効果測定までをご支援いたします。
CONTACT







