HubSpotの使い方を初心者向けに解説|まずやるべき基本設定と成果を出す機能
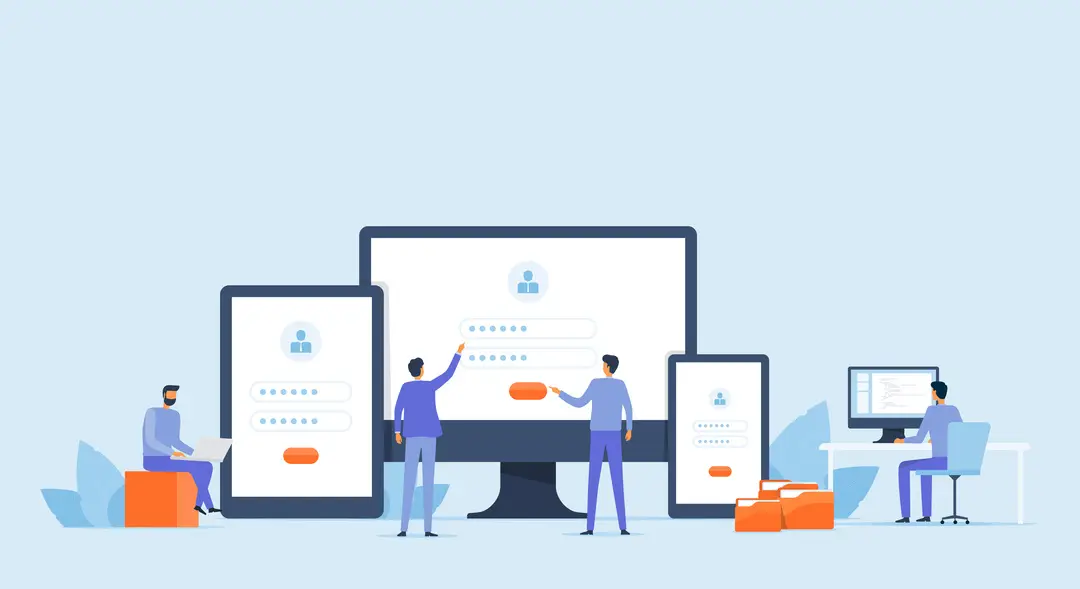
MAツールの導入・活用の相談はSells upへ。
MAツールの導入や、導入後の成果最大化に課題をお持ちでしたら、ぜひSells upにご相談ください。50社以上の導入・活用を支援してきた担当者が貴社の状況・目標に向き合い、最適なツールの導入プラン / 統計知識を用いた活用プラン描き、戦略策定から実装 / 実行 / 効果測定までをご支援いたします。
「HubSpotを導入したものの、機能が多すぎて何から手をつければ良いか分からない」
「高機能なツールだからこそ、使いこなせずに失敗してしまうのではと不安だ」
HubSpotの導入責任者を任されたマーケティング担当者や営業企画担当者の方から、このような声をよく聞きます。
HubSpotは、マーケティング、営業、カスタマーサポートまでを一元管理できる優れたプラットフォームですが、その多機能さゆえに、導入初期は戸惑うことも少なくありません。限られた時間の中で早期に成果を出すためには、全ての機能を一気に使おうとせず、「ビジネス成果に直結する最小限の機能」から着実に運用を始めることが重要です。
この記事は、単なる操作マニュアルではなく、HubSpotを初めて使う方が、導入初期につまずくことなく、最短で成果を出すための「最初のステップ」を具体的に解説します。BtoBビジネスの文脈で成果を出すためのSells up独自のノウハウも網羅していますので、ぜひ貴社のHubSpot活用にお役立てください。
HubSpotとは?導入初期につまずきやすいポイントと成功の秘訣
HubSpotを効果的に活用するためには、まずその全体像と、多くの企業が導入初期に直面する課題を理解しておくことが重要です。
HubSpotは「ツール」ではなく、ビジネスプロセスを統合する「基盤」
HubSpotは、単なる「顧客管理システム(CRM)」や「マーケティングツール」ではありません。本質は、マーケティング、営業、カスタマーサポートといった顧客接点を持つ部門の情報を一元管理し、分断されがちな業務プロセスを統合する「ビジネス基盤」です。
BtoBビジネスにおいて、「どの見込み客が、Webサイトで何を見て、現在どのような商談状況にあるのか」といった一連のデータフローを部門横断で可視化できる環境は、効率的なリード創出や受注率向上のために不可欠です。HubSpotは、この環境をノーコードで素早く構築できるという特徴があります。
HubSpotを構成する5つのHub(製品群)と役割
HubSpotは、共通のCRMデータベースを基盤とし、目的に応じて5つの「Hub」と呼ばれる製品群で構成されています。
CRM(顧客関係管理): 全てのHubの基盤。顧客情報や行動履歴を一元管理。(無料から利用可能)
Marketing Hub: WebサイトやEメールなどを通じてリード(見込み客)を獲得し、育成する。
Sales Hub: 商談の進捗管理(パイプライン管理)や営業活動の効率化を実現する。
Service Hub: 問い合わせ管理(チケット管理)など、顧客満足度を高める機能を提供する。
CMS Hub: HubSpot上でWebサイトやブログを構築・管理する。
これらのHubが連携することで、部門を横断したスムーズなデータ活用が可能になります。
なぜ多くの企業がHubSpotの活用に失敗するのか?よくある3つの原因
高機能なHubSpotですが、導入後に「結局、Excel管理から脱却できない」「現場が使いこなせず、定着しない」といった状況に陥るケースは少なくありません。その原因は、主に以下の3点に集約されます。
目的がない/不透明なまま導入:「何のために導入するのか」という目的が曖昧なまま進めてしまい、自社の業務フローにどう組み込むべきか定義できていない。
機能の詰め込みすぎ:最初から全ての機能を使いこなそうとして、情報過多になり現場が混乱してしまう。
運用ルールの未整備:「誰が、どのデータを、どのように管理するのか」という運用ルールが不明確なまま進行し、データが煩雑化してしまう。
これらの失敗は、導入初期の設計で回避できます。
【Sells upの視点】成功のポイントは「目的の明確化」と「スモールスタート」の徹底
Sells upが数多くのBtoB企業のHubSpot導入を支援する中で確信しているのは、「導入目的を関係者間で明確に合意形成し、最小単位で運用を開始する(スモールスタート)」ことの重要性です。
多機能ツールを導入する際、つい「あれもこれもできそう」と期待が先行しがちですが、現場のリソースは限られています。まずは以下のような形で、意図的に機能を制限することが肝要です。
最初は「Webからの問い合わせ情報の一元管理(CRM)」だけに目的を絞る。
マーケティング部門だけで試験運用し、成果と運用フローが確立してから営業部門へ展開する。
いきなり複雑な自動化(ワークフロー)を目指さず、手動での運用とデータ蓄積から始める。
HubSpotは、ビジネスの成長に合わせて機能を後から柔軟に追加・拡張できる設計になっています。まずは「小さな成功体験」を積み重ねることが、成果創出への最短の道筋となります。
HubSpot導入直後にやるべき3つの初期設定
ここからは、HubSpotを導入した直後に必ず取り組むべき、3つの基本的な初期設定を解説します。これらを正しく行うことで、後続のマーケティングや営業活動がスムーズに進みます。
Step.1:アカウントの基本情報を正しく設定する
まずは、アカウント全体に関わる基本情報を正確に入力します。設定画面の「アカウントの既定値」から、以下の項目を確認・設定しましょう。
会社名、所在地、業種
タイムゾーン(日本時間になっているか)
通貨(JPYになっているか)
この設定が曖昧だと、後でレポートの数値集計がずれたり、メールの差出人情報が誤って表示されたりするなど、思わぬトラブルの原因となります。特にタイムゾーンと通貨は、ビジネス上の意思決定に直結するため、最初に正確な情報を入力しておくことが非常に重要です。
Step.2:チームメンバーを招待し、適切な権限を割り振る
HubSpotは、複数メンバーでの利用を前提としたプラットフォームです。マーケティング、営業、カスタマーサポートなど、各業務に関わるメンバーを「ユーザー」として招待し、それぞれの役割に応じた「権限セット」を割り振りましょう。
権限設定のポイントは、「必要最小限の権限を付与する」ことです。
マーケティング担当者:「フォーム作成・配信」「Eメール」「リスト管理」権限
営業担当者:「取引(パイプライン)管理」「コンタクト・会社情報の閲覧・編集」権限
管理者(スーパー管理者):全ての機能へのアクセス権限
適切な権限管理は、情報漏洩リスクの低減だけでなく、メンバーが自身の業務に関係のない機能に惑わされず、集中できる環境を作る上でも重要です。
Step.3:トラッキングコードを自社サイトに設置する
HubSpotの大きな利点は、「顧客のWebサイト上の行動データ」を自動で取得し、CRMに蓄積できる点にあります。これを実現するためには、自社のWebサイトにHubSpotが発行する「トラッキングコード」を設置することが必須です。
これにより、以下のようなデータが自動で記録され、CRMやレポートに反映されます。
どの見込み客が、どのページを閲覧したか
フォーム送信や資料ダウンロードの履歴
配信したメールの開封やリンクのクリック状況
Web制作会社や社内のIT担当者と連携し、必ず最初に設定を完了させてください。
【Sells upの視点】BtoBにおけるトラッキング設定の重要性
トラッキングコードの設置は、単なるアクセス解析のためではありません。BtoBマーケティングにおいて重要なのは、「どのリードが」「何に興味を持っているか」を把握し、最適なタイミングでアプローチすることです。
例えば、あるリードが料金ページや導入事例ページを頻繁に閲覧している場合、導入検討の確度が高いと判断できます。HubSpotでは、こうした行動履歴が自動的にCRMのコンタクトレコードに時系列で記録されます。
このデータ蓄積が、後のマーケティング施策や営業アプローチの精度を大きく左右するため、導入の最も初期段階で確実に設定を終えておく必要があります。
【目的別】BtoBで成果を出すHubSpotの基本的な使い方
初期設定が完了したら、いよいよ具体的な業務でHubSpotを活用するフェーズです。ここでは、BtoB企業が成果を出すために必須となる基本的な使い方を、「ビジネス上の目的」別に解説します。単なる機能名だけでなく、何のためにその機能を使うのかを意識しましょう。
目的1:顧客情報を一元管理・分析したい(CRM機能)
すべての活動の土台となるのが「CRM(顧客管理)」機能です。バラバラだった顧客情報を集約し、分析可能な状態にします。
コンタクト(個人)と会社情報の管理方法
HubSpot CRMでは、顧客情報を「コンタクト」と「会社」という2つの主要なオブジェクトで管理します。
コンタクト:商談相手や問い合わせ担当者など、“個人”に関する情報。
会社:“組織”単位での情報(会社名、業種、従業員規模など)。
HubSpotは、この「コンタクト」と「会社」を自動的に紐付けて管理します。ExcelやCSVファイルで既存の顧客リストを一括インポートすることも可能です。
【Sells upの視点】データ移行の最重要ポイント:「名寄せ」と「カスタムプロパティ設計」
既存のExcelや他ツールからHubSpot CRMへデータを移行する際は、「名寄せ」と「カスタムプロパティの設計」がその後の活用度を大きく左右します。
特にBtoBの場合、会社名の表記揺れ(株式会社の有無、半角・全角の違いなど)を修正し、「会社ドメイン」などで一意性を保つ設計が不可欠です。「とりあえず全データをインポートする」というやり方は、CRMが煩雑化し管理不能になる典型的な失敗パターンです。
また、貴社独自の営業プロセスに合わせたカスタムプロパティを事前に設計しておくことが重要です。BtoBビジネスにおいては、以下のような項目の設定をおすすめします。
リードソース詳細:「展示会(○○展)」「ウェビナー(○月○日開催)」など、具体的な獲得経路。
MQL/SQL判定フラグ:営業へ引き渡す基準を満たしているかの管理。
ナーチャリング状況:「未着手」「フォロー中」「対象外」などの育成状況。
標準項目だけでは管理しきれない情報を定義することで、後々の分析やセグメンテーションが格段にしやすくなります。初期設計の手間を惜しまないことが、CRM活用の成功に直結します。
目的2:Webサイトから新規リードを獲得したい(フォーム・LP機能)
新規リードを獲得し、CRMに自動で登録するには、「フォーム作成」機能や「ランディングページ(LP)」機能を活用します。これらは無料プランから利用可能です。
フォームの作成手順と設置方法
HubSpotのフォームは、専門知識がなくても直感的な操作で作成できます。
管理画面から「マーケティング」→「フォーム」を選択。
テンプレート(例:お問い合わせ、資料請求)を選び、必要な項目をドラッグ&ドロップで追加。
完成したフォームは、HubSpot内のLPや、既存の自社Webサイトに簡単に埋め込み可能。
フォーム経由で送信された情報は、自動でHubSpot CRMの「コンタクト」として登録されるため、手作業でのリスト作成は不要になります。
【Sells upの視点】BtoBフォームで設定すべき必須項目と離脱を防ぐ工夫
BtoBビジネスにおけるリードフォームの目的は、「営業がアプローチすべき質の高いリードか判断するための情報」を収集することです。そのため、「会社名」「部署・役職」「業種」「従業員規模」といった項目を設計しておくことが重要です。
しかし、入力項目が多すぎるとユーザーの負担が増え、離脱率が高まります。これを解消するためには、以下の工夫が有効です。
「必須項目」と「任意項目」を明確に分ける。
選択式の項目(プルダウンやチェックボックス)を多用し、手入力を減らす。
リードの「質」と「量」のバランスを見極め、入力負荷を最小限に抑える設計が成果に直結します。
目的3:獲得したリードを育成したい(Eメールマーケティング機能)
獲得したリードに対して、定期的な情報提供やナーチャリング(育成)を行うには、「Eメールマーケティング」機能が有効です。CRMデータと連携し、パーソナライズされたメール配信を簡単に行えます。
メール作成から配信、効果測定までの流れ
メール配信の基本的な流れは以下の通りです。
「マーケティング」→「Eメール」から新規メールを作成。
テンプレートを活用し、内容を編集。
配信対象となる「リスト」(例:〇〇資料ダウンロード者)を選択し、配信。
配信後は、開封率、クリック率などの効果測定データが自動で可視化されます。また、誰がどのメールを開封したかといった個別の反応もCRMに記録されます。
【Sells upの視点】BtoBメールの効果測定で見るべきは「商談化への貢献度」
BtoBのメールマーケティングにおいて、開封率やクリック率は重要ですが、それだけをKPIとして追いかけるのは不十分といえます。
最終的な目的は、メールを通じてリードの関心度を高め、商談に繋げることです。そのため、効果測定では単なるエンゲージメント指標だけでなく、「そのメール配信がどれだけMQL創出や商談化に貢献したか」までを計測する視点が求められます。HubSpotのレポート機能を活用し、「特定のメールキャンペーン経由での商談化率」を分析することで、営業成果に貢献するPDCAサイクルを回すことが可能になります。
目的4:営業の案件進捗を可視化・効率化したい(パイプライン管理機能)
営業活動の進捗状況を可視化し、組織全体の受注率向上を目指す上で欠かせないのが「パイプライン管理」機能です。HubSpotではこれを「取引」と呼びます。
営業プロセスに合わせたパイプラインの作成と案件管理の方法
「セールス」→「取引」画面では、自社の営業プロセスに合わせてパイプラインのステージを自由に設計できます。
ステージの設計例:新規アプローチ → ヒアリング済み → 提案済み → 見積もり提示 → 交渉中 → 受注(または失注)
案件(取引)はカード形式で表示され、現在のステージをドラッグ&ドロップで直感的に移動できます。各取引カードには、金額、担当者、商談履歴、次回アクションなどが一元管理されます。
また、案件ごとに「タスク」を設定し、ToDoリストやリマインダーで担当者の活動を管理することで、商談の停滞やフォロー漏れを防ぎます。
【Sells upの視点】成約率を高めるパイプライン設計と「出口条件」の重要性
パイプライン管理を成功させるポイントは、自社の営業活動の実態に即したステージ設計と、その運用ルールを明確に定義することです。特に重要なのが、各ステージにおける「出口条件(次のステージに進めるための基準)」を言語化し、チーム内で統一することです。
例えば、「ヒアリング済み」から「提案済み」に進めるためには、「BANT情報(予算・決裁者・必要性・導入時期)が確認できていること」といった具体的な条件を設定します。
この出口条件が曖昧なまま運用されると、担当者の主観でステージが移動してしまい、パイプラインの精度が著しく低下します。「なんとなく進んでいる」状態を排除し、属人化を防ぐことで、組織全体の成約率の底上げが図れます。
目的5:顧客からの問い合わせ対応を効率化したい(チケット管理機能)
HubSpotは、営業やマーケティングだけでなく、導入後の顧客サポートや問い合わせ対応も一元管理できる「Service Hub」を提供しています。その中心となるのが「チケット」管理機能です。
問い合わせを一元管理し、対応漏れを防ぐ方法
「サービス」→「チケット」機能では、顧客からの問い合わせやサポート依頼を「チケット」として発行し、管理できます。
メールやチャットなど、様々なチャネルからの問い合わせを自動でチケット化。
各チケットに優先度、担当者、現在のステータス(例:未対応、対応中、解決済み)を設定。
これにより、誰がどの問い合わせに対応しているかが一目で分かり、対応漏れや二重対応を防ぐとともに、チケットがCRMの顧客情報と紐づくため、過去のやり取りを踏まえた適切なサポートができるようなります。
【Sells upの視点】チケット管理を「顧客ニーズの収集源」として活用する
カスタマーサポートに寄せられる声は、製品の改善点や顧客の新たなニーズを発見する貴重な情報源です。サポート対応中に顕在化した課題や要望は、アップセルやクロスセルの絶好の機会にもなり得ます。
チケット管理機能を「単なる問い合わせ対応の効率化」に留めず、「顧客ニーズの可視化」や「営業部門への追加提案のトスアップ」の仕組みとして活用することが重要です。こうした視点を持つことで、LTV(顧客生涯価値)の最大化が図れます。
HubSpot活用の優先順位:「最初の90日間」で成果を出すためのプラン
HubSpotの基本機能は理解できたものの、「結局、自社では何から手をつけるべきか」と悩む方は多いでしょう。多機能ゆえに、優先順位を誤ると成果が出るまでに時間がかかり、現場のモチベーションも低下してしまいます。
ここでは、BtoB企業がHubSpot導入後の「最初の90日間」で取り組むべきことと、その順番を具体的に提案します。この手順で進めることで、失敗なく最初のステップを踏み出すことができます。
最初の30日間(1ヶ月目):データ基盤の構築とリード獲得の仕組み作り
導入直後の1ヶ月間は、将来的な活用を見据えた「データ基盤の構築」に注力します。ここで焦って施策を実行しないことが重要です。
目標:顧客情報を一元管理し、Webからの新規リード獲得経路を確立する。
やるべきこと:
初期設定の完了(特にトラッキングコード設置)。
既存顧客データのインポートと名寄せ(目的1:CRM)。
カスタムプロパティの設計と設定(目的1:CRM)。
主要なフォーム(お問い合わせ、資料請求)の作成と設置(目的2:フォーム)。
まずは、HubSpot CRMを今後のマーケティング・営業活動の土台として整備することを最優先とします。
31日目〜60日目(2ヶ月目):営業活動の可視化とリードへのアプローチ開始
データ基盤が整ったら、次は「営業活動の効率化」と「リードへのアプローチ」に着手します。
目標:営業案件の進捗を可視化し、獲得したリードへの初期アプローチを開始する。
やるべきこと:
営業パイプライン(取引)の設計と設定(目的4:パイプライン)。
営業担当者へのHubSpot利用トレーニングと運用開始。
セグメントリストの作成(例:新規リード、特定の業種のリード)。
簡単なメールマガジンの配信開始(目的3:Eメール)。
この段階で、マーケティングが獲得したリードが、営業のパイプライン上でどのように管理されていくか、部門を横断した一連の流れ(データフロー)を確立させます。
61日目〜90日目(3ヶ月目):効果測定と改善サイクルの確立
運用が回り始めたら、蓄積されたデータを分析し、「効果測定と改善」のサイクルを回し始めます。
目標:各施策の効果を測定し、データに基づいた改善点を見つけ出す。
やるべきこと:
ダッシュボードやレポート機能を使った現状分析(リード獲得数、商談化数など)。
フォームのCVR(コンバージョン率)改善(項目見直しなど)。
メールの開封率・クリック率改善(件名やコンテンツの見直し)。
パイプラインのボトルネック分析と改善策の検討。
この90日間のプランを通じて、HubSpot活用の基本的な流れを体験し、早期に成功体験を得ることを目指します。
HubSpotの無料プランと有料プラン:アップグレードの判断基準
HubSpotを導入する際、「まずは無料プランから始めるべきか」は多くの企業が悩むポイントです。
まずは無料プランでできることを徹底的に試す
HubSpotは、無料プラン(Free Tools)でも非常に幅広い機能を提供しており、BtoBビジネスの基礎的な活動は十分にカバーできます。
無料プランで実現できる主なこと:
顧客情報の一元管理と履歴の自動蓄積(CRM)。
シンプルなフォーム・LPの作成とリード獲得。
Eメール配信(月2,000件まで、HubSpotロゴ表示あり)。
案件(取引)のパイプライン管理(制限あり)。
導入初期においては、まず「無料でどこまで自社の業務フローに適合し、成果を出せるか」を徹底的に試してみることをお勧めします。
【具体例】無料プランを最大限活用したリード獲得・育成シナリオ
無料機能だけでも、以下のような一連の仕組みを構築することが可能です。
リード獲得:無料フォームでホワイトペーパーの資料請求を受け付ける。
データ蓄積:リード情報は無料CRMに自動登録され、トラッキングコードによりWeb閲覧履歴も蓄積される。
リード育成:無料Eメール機能で定期的にメルマガを配信し、関係性を維持する。
アプローチ:リードの反応(メール開封や料金ページの閲覧など)を見て、営業がアプローチする。
案件管理:無料のパイプライン管理で案件進捗を管理する。
このように、まずは無料で成果を体験し、現場の運用にフィットするかを見極めることが、無駄な投資や混乱を防ぐ重要なポイントです。
目的別:いつ有料プラン(Starter以上)にアップグレードすべきか?
無料プランの運用を通じて、「もっと効率化したい」「自動化したい」といった具体的な課題が見えてきた時が、有料プラン(Starter、Professional、Enterprise)へのアップグレードを検討するタイミングです。
以下に、BtoBビジネスでよくある目的ごとに、アップグレードを検討すべき判断基準をまとめました。
目的 | アップグレードを検討するタイミングの例 | 有料プランで実現できること(例) |
|---|---|---|
| リード獲得の強化 | ・フォームやLPからHubSpotのロゴを消したい。 | ・HubSpotロゴの非表示。 |
| マーケティングの自動化 | ・リードの属性や行動に応じて、メール配信を自動化したい(ステップメールなど)。 | ・MA機能(ワークフロー)による複雑な自動化。 |
| 営業活動の高度化 | ・複数の製品やサービスごとにパイプラインを分けたい。 | ・複数パイプラインの設定。 |
| サポート体制の強化 | ・問い合わせ対応のSLA(対応期限)を管理したい。 | ・SLA管理、自動割り当て。 |
公式リソースを活用して自走できる体制を作る
HubSpotを長期的に使いこなし、成果を出し続けるためには、外部の支援だけに頼らず、社内で知識を蓄積し「自走」できる体制を作ることが不可欠です。HubSpotは、学習のための公式リソースが非常に充実しています。
HubSpotナレッジベース:機能の設定方法やトラブルシューティングに関する詳細なドキュメント集。
HubSpotアカデミー:無料で受講できるオンライン講座と認定資格プログラム。体系的な学習に最適。
HubSpotコミュニティー:世界中のユーザーと情報交換や質問ができる場。
これらのリソースを積極的に活用し、担当者のスキルアップを図ることが、HubSpotの価値を最大化することに繋がります。
まとめ:HubSpotを使いこなし、ビジネス成長を実現するために
この記事では、HubSpotの基本的な使い方から、BtoBビジネスで成果を出すための具体的な活用方法までを解説してきました。
HubSpotは、顧客情報を一元管理し、マーケティング、営業、サポートの連携を強化することで、ビジネスの成長を支援するプラットフォームです。しかし、その多機能さゆえに、導入初期の進め方を誤ると、活用が進まずに終わってしまうリスクもあります。
成功のための重要なポイントは、以下の3点です。
目的の明確化:何のためにHubSpotを使うのかを明確に定義する。
スモールスタート:最初は機能を絞り込み、最小単位で運用を開始する。
段階的な拡張:成果と習熟度に合わせて、段階的に活用範囲を広げていく。
まずは無料プランから始め、この記事で紹介した「最初の90日間プラン」を参考に、貴社のビジネスに合わせた活用方法を見つけてください。
MAツールの導入・活用の相談はSells upへ。
MAツールの導入や、導入後の成果最大化に課題をお持ちでしたら、ぜひSells upにご相談ください。50社以上の導入・活用を支援してきた担当者が貴社の状況・目標に向き合い、最適なツールの導入プラン / 統計知識を用いた活用プラン描き、戦略策定から実装 / 実行 / 効果測定までをご支援いたします。
CONTACT







