成果を最大化するBtoBの顧客ランク分け|分析手法からSFA/MA連携、運用定着まで徹底解説
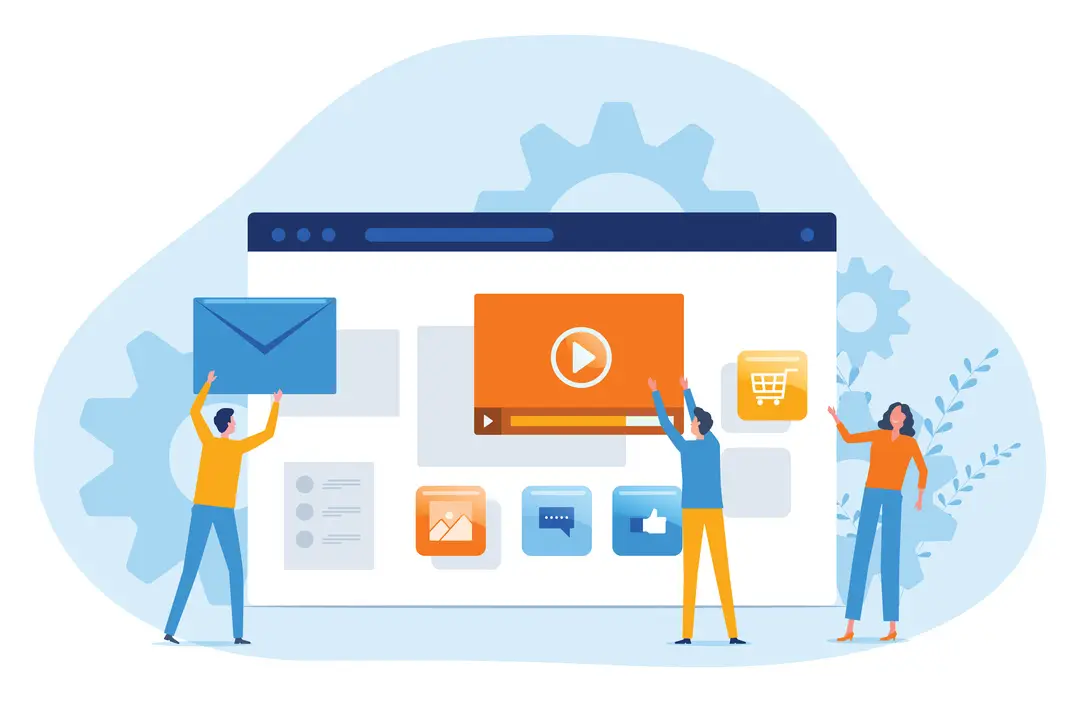
MAツールの導入・活用の相談はSells upへ。
MAツールの導入や、導入後の成果最大化に課題をお持ちでしたら、ぜひSells upにご相談ください。50社以上の導入・活用を支援してきた担当者が貴社の状況・目標に向き合い、最適なツールの導入プラン / 統計知識を用いた活用プラン描き、戦略策定から実装 / 実行 / 効果測定までをご支援いたします。
BtoBビジネスにおいて、蓄積された顧客データを営業やマーケティング活動に有効活用できていない、という課題はないでしょうか。SFA(営業支援システム)やCRM(顧客関係管理)を導入していても、データが「ただ蓄積されているだけ」の状態では、ビジネスの成長にはつながりません。
また、営業活動が担当者の経験や勘に依存し、属人化しているケースも少なくありません。限られた人的リソースや予算の中で、どの顧客に優先的にアプローチすべきかの判断基準が曖昧なままでは、組織全体の営業効率化は困難です。
こうした「データ活用の形骸化」と「営業活動の属人化」という課題を解決し、データに基づいた客観的な基準でリソース配分を最適化する手法が「顧客ランク分け」です。
本記事では、BtoBにおける顧客ランク分けの重要性から、具体的な分析手法、そしてSFA/MA(マーケティングオートメーション)を活用して業務プロセスに組み込み、継続的に成果を出すための仕組み作りまでを解説します。
なぜ、BtoBで顧客ランク分けが重要なのか?
顧客ランク分けは、単なる顧客リストの分類作業ではなく、事業成果を向上させるための、営業・マーケティング戦略の基盤となる取り組みといえます。
属人化した営業からの脱却と組織的な標準化
営業担当者ごとの経験や勘に頼ったアプローチでは、組織全体でのパフォーマンスにばらつきが生じます。顧客ランク分けにより、データに基づいた客観的な基準が設けられ、誰が担当しても一定の品質で、優先順位に基づいた顧客対応ができる体制を構築できます。これは、営業活動の標準化と組織力の底上げに直結します。
限られたリソースの最適配分とROI向上
全ての顧客に対して均等にリソースを投下するのは効率的ではありません。顧客がもたらす価値(売上貢献度)や将来の成長余地に応じて、営業やマーケティングのリソース配分を最適化することが重要です。顧客ランク分けは、投資対効果(ROI)を向上させるための意思決定を可能にします。
80:20の法則(パレートの法則)に基づく優良顧客の特定
多くのBtoB企業において、「全顧客のうち上位20%が売上の80%を生み出す」というパレートの法則が当てはまると言われます。顧客ランク分けを通じてこの上位20%にあたる優良顧客を明確に特定し、リソースを集中投下することで、効率的な売上成長を実現できます。
LTV(顧客生涯価値)の向上とデータ活用基盤の構築
顧客ランクに応じて最適な施策を実行することで、顧客満足度とエンゲージメントが高まり、結果としてLTV(ライフタイムバリュー:顧客生涯価値)が向上します。優良顧客との関係性を強化してアップセルやクロスセルを促進すると同時に、離反の兆候がある顧客を早期に検知するためにも重要です。
また、顧客ランク分けのプロセスを通じて、SFA/CRMに蓄積されたデータをビジネスに活用する基盤が整い、「データをただ蓄積しているだけ」の状態から脱却できます。
顧客ランク分けの代表的な分析手法とBtoBでの応用
BtoB領域で有効な顧客ランク分けの手法は複数存在します。自社のビジネスモデルや目的に合わせて、適切な手法を選択、あるいは組み合わせることが重要です。
【手法1】デシル分析:購入金額によるシンプルな現状把握
デシル分析は、全顧客を累計購入金額の多い順に並べ、均等な人数で10のグループ(デシル)に分けて分析する手法です。例えば、1,000社の顧客がいれば、100社ずつのグループに分けます。計算が容易で、売上貢献度の高い顧客層を素早く特定するのに適しています。
デシル分析のメリットと注意点
メリット:
Excelやスプレッドシートでも容易に実行でき、導入しやすい。
売上構成比を客観的な数値で把握できる。
注意点:
過去の累計金額のみを基準とするため、直近の取引状況や取引頻度が反映されない。
一時的に大口の取引があった顧客が上位に入り、継続的な優良顧客と区別できない場合がある。
BtoBにおいては、現状の売上構造を把握する最初のステップとして有効ですが、これ単体でのランク分けでは不十分な場合があります。
【手法2】RFM分析:多角的な視点での顧客評価
RFM分析は、以下の3つの指標を用いて顧客を評価し、ランク分けする手法です。
Recency(最終購入日・最終取引日):直近で取引があった顧客ほど高評価。
Frequency(購入頻度・取引回数):取引頻度が高い顧客ほど高評価。
Monetary(購入金額・取引総額):累計購入金額が多い顧客ほど高評価。
各指標にスコア(例えば5段階評価)を設定し、その合計点で顧客の価値を測ります。
RFM分析のメリットとBtoBにおける注意点
メリット:
購入金額だけでなく、取引の活発度も考慮できる。
休眠状態にある顧客や、離反しそうな顧客の発見に役立つ。
注意点:
BtoBの場合、商材によっては取引頻度(Frequency)が少なくても高価値な顧客(例えば、大型設備や基幹システムなど)が存在するため、指標の重み付け調整が必要。
SaaSのようなサブスクリプションモデルでは、購入金額(Monetary)よりも契約期間や利用状況の方が重要になる場合がある。
【手法3】BtoB特有の複雑性を反映した複合指標モデル
BtoBビジネスでは、デシル分析やRFM分析のような購買行動だけでなく、企業属性やエンゲージメント度合いなど、多様なデータを組み合わせた複合的な指標でのランク分けが有効です。購買プロセスが長期かつ複雑であり、決裁者が複数存在するBtoBの特性を反映することで、精度の高い顧客分類が可能になります。
BtoBで重視すべき3つの指標群
BtoBにおけるランク分けでは、主に以下の3つの側面から指標を選定し、スコアリングモデルを構築します。
1. 企業属性:ポテンシャルの評価
ターゲットとする企業の属性情報です。自社にとって理想的な顧客像(ICP:Ideal Customer Profile)とどれだけ合致しているか、将来的な取引拡大の可能性(ポテンシャル)を評価します。
業種、業界
企業規模(従業員数、売上高)
所在地(エリア)
上場区分、成長率
2. 取引実績と関係性:LTVの評価
過去から現在に至るまでの取引の実績や、顧客との関係性の深さを評価します。
累計取引金額、年間取引額(SaaSの場合はARR/MRR)
契約期間、継続年数
導入製品・サービス数(クロスセル状況)
アップセル履歴
決裁者や重要人物とのコネクション度合い
導入部署の拡大状況
3. エンゲージメントと行動:関心度の評価
Webサイト上での行動やマーケティング施策への反応など、顧客の関心度や積極性を評価します。主にMAツールなどで計測します。
Webサイトの閲覧履歴(料金ページ、事例ページなど)
資料ダウンロード履歴
セミナーやイベントへの参加履歴
メールの開封率、クリック率
製品・サービスの利用頻度、ログイン状況(SaaSの場合)
BtoB SaaS企業における指標設定の考え方
例えば、従業員300名規模のBtoB SaaS企業の場合、以下のような指標の組み合わせが考えられます。
企業属性:ターゲット業種、従業員数(自社の主要顧客層に合致するか)
取引実績:年間契約額(ARR)、契約プラン(上位プランほど高評価)、利用ユーザー数
エンゲージメント:直近1ヶ月の製品ログイン回数、特定機能の利用状況(活用度)、サポートへの問い合わせ内容
これらの指標を組み合わせることで、「契約額は大きいが最近利用頻度が落ちている顧客」や「契約額は小さいが利用が活発でアップセル余地のある顧客」などを明確に区別できます。
【Sells upの視点】BtoBの指標設定は「LTVの予測精度」と「静的・動的データ」の組み合わせが重要
BtoBビジネスにおける顧客ランク分けの指標設定で重要なのは、「将来のLTV(顧客生涯価値)をいかに正確に予測できるか」という視点です。単に過去の売上金額だけで評価すると、今後の成長余地を見落とす可能性があります。例えば、SaaS企業であれば、売上金額(MRR)だけでなく、「製品の利用頻度」や「活用度」といったエンゲージメント指標が、将来の契約更新やアップセルを予測する上で重要になります。
また、企業属性のような変化しにくい「静的データ」と、エンゲージメントのような日々変化する「動的データ」を組み合わせることも成功のポイントです。静的データは顧客のポテンシャル(潜在的な価値)を示し、動的データは顧客の現状(関心度や利用状況)を示します。
SFA/MAツールを用いて、企業属性スコア(静的)と行動スコア(動的)を掛け合わせたマトリクスで顧客を分類すれば、「ポテンシャルは高いがまだ関心が低い顧客」にはマーケティング部門がナーチャリングを行い、「ポテンシャルが高く関心も高い顧客」には営業部門が即座にアプローチする、といった具体的なアクションプランに落とし込めます。
SFA/MAを活用した効率的で「動的な」顧客ランク管理
顧客ランク分けをExcelなどの手動で行うには限界があります。データの集計や更新に多大な工数がかかり、リアルタイム性も失われるため、せっかく分類してもすぐに有効性が低下してしまいます。
BtoBビジネスで顧客ランク分けを成果につなげるためには、SFA/MAの活用が不可欠です。
手動管理の限界とツール導入の必要性
顧客データは日々変化します。手動での管理では、この変化に追随できず、古い情報に基づいた誤ったアプローチを行ってしまうリスクがあります。SFA/MAを導入することで、データの一元管理と自動集計が可能となり、常に最新の顧客状態に基づいたランク管理が実現します。これにより、担当者の作業負担も軽減されます。
複数指標を組み合わせた自動スコアリングの設定
SFA/MAツールでは、前述した「企業属性」「取引実績」「エンゲージメント」といった複数の指標データを組み合わせ、自動でスコアリングを行う設定が可能です。
例えば、「資料ダウンロード:+5点」「料金ページ閲覧:+10点」「ターゲット業種:+15点」のように、ビジネスモデルに合わせてスコアの重み付けや条件を柔軟に設定できます。この自動化により、客観的で精度の高い顧客ランク分けが効率的に行えます。
ランクの自動更新とリアルタイムな状況把握
SFA/MAを活用するメリットは、顧客ランクを「動的」に管理できる点です。顧客の行動(例えば、セミナー参加)や取引状況の変化(例えば、契約更新)が発生した際に、スコアが変動し、それに基づいてランクが自動で更新される仕組みを構築できます。
これにより、営業やマーケティング担当者は、常に最新の顧客ランクに応じた最適なアプローチを、タイムリーに実行できるようになります。機会損失や対応遅れを防ぎ、組織全体の生産性向上に寄与します。
顧客ランク分けを導入するための具体的な手順
顧客ランク分けを自社に導入し、運用を軌道に乗せるためには、明確なプロセスに沿って進めることが重要です。以下のStepに従って着実に推進しましょう。
Step.1 目的とゴールの明確化
最初に、なぜ顧客ランク分けを行うのか、その目的を明確に定義します。目的が曖昧なままでは、適切な指標選定や施策立案ができず、取り組みが形骸化してしまいます。
目的の例:
優良顧客へのリソース集中によるLTV向上。
休眠顧客の掘り起こしによる売上機会創出。
MQL(Marketing Qualified Lead)の質向上と商談化率改善。
具体的なKPI(例えば、SQL転換率15%向上、アップセル売上前年比20%増)も設定し、関係者間で共有します。
Step.2 データの収集と整備(データクレンジングと統合)
次に、SFA/CRM、販売管理システム、MAツールなどに分散している顧客データを集約し、分析可能な状態に整備します。この「データ整備」の工程が、ランク分けの精度を左右する重要なポイントです。
データクレンジング:企業名の表記ゆれ(例えば、株式会社と(株))、重複データの統合(名寄せ)、古い情報や誤った情報の修正・削除を行います。
データ統合:分散しているデータをSFA/MAに統合し、一元管理できる体制を構築します。
正確なデータがなければ、分析結果の信頼性は担保できません。
【Sells upの視点】「使えるデータ」を整備することが最初の関門
顧客ランク分けを試みる企業の多くが直面するのが、「データが整備されておらず、分析できる状態にない」という課題です。SFA/MAを導入していても、入力ルールが徹底されていなかったり、システム間のデータ連携がうまくいっていなかったりすると、正しいランク分けはできません。
データ整備は地道な作業ですが、ここを乗り越えなければデータドリブンな営業・マーケティングは実現しません。まずは自社のデータが「使える状態」になっているかを確認することが、最初のステップとなります。Sells upでは、顧客ランク分けの仕組み作りと並行して、SFA/MAのデータ整備や入力ルールの標準化といった、データ基盤の構築支援を重視しています。
Step.3 分析手法と評価指標(スコアリングモデル)の選定
Step.1で定めた目的に基づき、最適な分析手法と評価指標を選定します。BtoBビジネスにおいては、前述した「BtoB特有の複合指標モデル」をベースに、自社のビジネスモデルに合わせて指標をカスタマイズすることを推奨します。
どの指標をどれくらいの重みで評価するか、スコアリングモデルのルールを設計します。
Step.4 ランク分けの実行とシステムへの実装
選定した手法と指標に基づき、実際に顧客ランク分けを実行します。SFA/MAツールを利用する場合は、設計したスコアリングルールやランク定義をシステム上に設定し、自動でランクが付与されるように実装します。
結果はダッシュボードやレポートで可視化し、関係者が直感的に状況を把握できるように整備します。
Step.5 ランク定義の明文化と部門間での共有
各ランク(例えば、Aランク、Bランク、Cランクなど)の定義、評価基準、そして各ランクに対する推奨アクションを明確に言語化します。
この定義は、マーケティング、インサイドセールス、フィールドセールス、カスタマーサクセスといった関連部門全体で共有し、共通認識を持つことが不可欠です。これにより、部門を超えた一貫性のある顧客対応が可能になります。
ランクに応じた最適なアプローチ戦略と部門間連携
顧客ランク分けは、実行して終わりではありません。分類した各ランクに対して、最適なアプローチを設計し、実行することで初めて成果につながります。ここでは、代表的なランクごとの施策例と、それを実現するための部門間連携(ワークフロー)について解説します。
【Aランク】優良顧客:LTV向上とロイヤルティ向上
Aランク顧客は、現在の売上の大部分を支える重要顧客層です。関係維持を最優先としつつ、アップセル・クロスセルによるLTV向上と、ロイヤルティ向上を目指します。個別最適化されたハイタッチな対応が求められます。
マーケティング施策例:
限定コミュニティやユーザー会への招待。
新機能や上位サービスの先行案内、β版提供。
経営層向けのエグゼクティブセミナー開催。
営業・CS施策例:
カスタマーサクセスによる手厚い導入支援と活用促進。
QBR(四半期ビジネスレビュー)の実施による成果共有と次期提案。
担当役員や経営層による定期訪問。
部門間連携のポイント:CS部門が把握した顧客の活用状況や新たな課題を、SFAを通じて営業部門へスムーズに共有し、タイムリーなアップセル提案につなげる連携フローが重要です。
【Bランク】見込み顧客(育成対象):ランクアップ促進と商談化
Bランク顧客は、現状の取引は中規模であるものの、将来的な成長が期待できる層です。積極的な情報提供と関係構築を通じて、Aランクへの昇格を目指します。ハイタッチとテックタッチ(テクノロジーを活用したアプローチ)を組み合わせた対応が有効です。
マーケティング施策例:
課題解決型のウェビナーやワークショップの案内。
導入事例や活用ノウハウに関するコンテンツ提供。
MAを活用したセグメント別のパーソナライズドメール配信。
営業・CS施策例:
インサイドセールスによる定期的な状況ヒアリングとニーズ把握。
課題に合わせた個別提案の実施。
商談化を促進するキャンペーンや限定オファーの展開。
部門間連携のポイント:マーケティング部門が創出したMQLに対し、インサイドセールスが迅速に架電し、ヒアリングした情報をSFAに記録してフィールドセールスへトスアップする、一連のワークフロー(業務の流れ)を整備します。
【Cランク】休眠・低位顧客:効率的なフォローと再活性化
Cランク顧客は、過去に取引があったものの現在は休眠している顧客や、取引規模が小さい顧客層です。リソースをかけすぎず、効率的にフォローしながら、再活性化(掘り起こし)を目指します。テックタッチ中心の対応が基本となります。
マーケティング施策例:
MAツールを活用した自動メールフォロー。
最新の業界トレンド情報や製品アップデート情報の提供。
再購入や再利用を促す特別キャンペーンの案内。
営業・CS施策例:
インサイドセールスによるメールやコールでの状況確認(優先度は下げる)。
セルフサーブで利用できるコンテンツやFAQの充実。
部門間連携のポイント:MAツールで再活性化の兆候(例えば、Webサイトへの再訪問、メールクリック)を検知した場合、自動でインサイドセールスにタスクを割り振る仕組みを構築し、効率的に対応します。
ランク変動をトリガーにしたLTV向上サイクル
顧客の状況は常に変化するため、顧客ランクも固定的なものであってはなりません。SFA/MAツールを活用し、顧客ランクの変動をトリガー(引き金)として自動でアクションを実行する仕組みを構築することで、LTV向上のサイクルを継続的に回すことができます。
ランクアップ・ダウンを自動検知する仕組み
SFA/MAツールでは、スコアや特定の指標が設定した閾値を超えたり下回ったりしたタイミングで、自動的にランクを変更し、担当者に通知する設定が可能です。この仕組みにより、顧客の変化の兆候をリアルタイムに把握し、即座に対応できます。
ランクダウンの兆候を捉えた離反防止
例えば、SaaSビジネスにおいて「ログイン頻度の低下」「特定機能の利用停止」「サポートへの問い合わせ内容の変化」といったランクダウンの兆候を検知した場合、離反(チャーン)のリスクが高まっています。
こうした兆候を捉えたら、即座にカスタマーサクセス担当者へ自動アラートを通知し、個別のヒアリングを実施したり、活用促進のための特別なサポートを提供したりするなど、先回りした離反防止アプローチが重要です。
ランクアップした顧客へのタイムリーなアップセル提案
顧客がCランクからBランク、あるいはBランクからAランクに昇格した場合(例えば、利用ユーザー数の増加、エンゲージメントスコアの向上)は、アップセルやクロスセルの良い機会です。
SFA/MAの自動アラートやワークフロー機能を活用し、営業担当者が適切なタイミングで提案活動を行えるようにすることで、売上機会を逃さず捉えることができます。
【Sells upの視点】部門間を横断するワークフロー設計が「動的な管理」の要
動的な顧客ランク管理を実現するためには、SFA/MAの設定だけでなく、部門間を横断するワークフローの設計が不可欠です。ランクが変動した際に、「誰が」「いつ」「どのように」対応するのかを明確に定義し、システムに実装する必要があります。
例えば、マーケティングが獲得したリードのエンゲージメントが高まりランクアップした際、インサイドセールスにいかにスムーズに引き渡すか。また、受注後にカスタマーサクセスがランクダウンの兆候を検知した際に、どの部門が主導して対応するのか。
こうした部門間の連携が円滑でなければ、せっかくのランク分けも機能しません。特にThe Model型のような分業体制をとる組織では、部門間の引き継ぎルールが曖昧になりがちです。Sells upでは、マーケティングからカスタマーサクセスまで一気通貫したワークフロー設計と、それを実現するためのSFA/MAの最適化を支援しています。
顧客ランク分けの成果測定(ROI)と評価
顧客ランク分け施策がビジネス上の成果にどれだけ貢献したかを測定・評価することは、取り組みを継続し、改善していく上で重要です。抽象的な評価に留まらず、具体的なKPIを設定してROI(投資対効果)を測定しましょう。
評価すべき主なKPIと測定方法
顧客ランク分けの成果を測るためには、導入時に設定した目的に応じて、以下のようなKPIを設定します。
ランク変動の推移:期間ごとの各ランクの顧客数や売上構成比の変動を確認します。BランクからAランクへ昇格した顧客数など、ランクアップの状況を追跡します。
ランク別のLTV変化:ランク分け導入前後で、各ランクのLTVがどのように変化したかを測定します。
商談化率・成約率の改善:MQLからのSQL転換率や、SQLからの成約率が改善したかを確認します(ペルソナの目標に対応)。
アップセル・クロスセル率:既存顧客からのアップセル・クロスセルによる売上が増加したかを測定します(ペルソナの目標に対応)。
営業活動の効率化:顧客あたりの訪問回数や対応コストがどのように変化したか、営業担当者の生産性が向上したかを評価します。
これらのKPIは、SFA/CRMのレポーティング機能やダッシュボードを活用して定期的にモニタリングします。
ROIの考え方
顧客ランク分けのROIは、施策によって得られた利益(売上向上額、コスト削減額)を、施策にかかったコスト(ツール導入費用、データ整備費用、人件費など)で割って算出します。
例えば、優良顧客へのリソース集中によりアップセル売上が増加し、一方で低位顧客への対応コストが削減された場合、その合計が投資効果となります。定量的なROIを算出することで、経営層や他部門への説明責任を果たし、取り組みの重要性への理解を促進できます。
顧客ランク分けを成功させるためのポイントと注意点
顧客ランク分けを導入し、運用を定着させる過程では、いくつかの課題に直面することがあります。ここでは、BtoB企業が陥りがちな失敗を回避し、成功に導くためのポイントを整理します。
最初から完璧を目指さず、スモールスタートで始める
最初から複雑な指標や完璧な運用体制を目指すと、準備に時間がかかりすぎたり、現場が混乱したりする原因となります。まずは入手しやすいデータとシンプルな基準(例えば、デシル分析から始める、主要な2〜3の指標でスコアリングする)でスモールスタートを切り、運用しながら課題を発見し、段階的に精度を高めていくアプローチが現実的です。
データの精度と鮮度を維持する仕組み作り
顧客ランク分けの基盤となるのはデータです。データが不正確であったり、古かったりすると(データの不備)、ランク分けの信頼性が損なわれます。
データの精度:入力ルールの徹底や、定期的なデータクレンジングを実施します。
データの鮮度:SFA/MAを活用し、常に最新の情報が反映される仕組みを構築します。
データマネジメントの体制構築も並行して進めることが重要です。
営業部門をはじめとする現場との連携を密にする
顧客ランク分けは、マーケティング部門だけで完結するものではありません。実際に顧客と接点を持つ営業部門やカスタマーサクセス部門の協力が得られなければ、施策は形骸化します(現場の非協力)。
ランクの定義や運用ルール(指標選定)を策定する段階から現場の意見を取り入れ、共通認識を持つことが重要です。指標設定が現場の感覚と乖離すると、「このランク分けは実態に合っていない」という不満が生じるケースがあります。現場からのフィードバックを反映させる仕組みも必要です。
定期的な見直しと改善を怠らない
市場環境や顧客の行動は常に変化します。導入時に設定したランク分けの基準や指標も、時間とともに実態と合わなくなる可能性があります。
半期や1年に一度など、定期的に基準や運用方法を見直し、現状に合わせてアップデート(チューニング)し続けることが、成果を出し続けるためのポイントです。
【Sells upの視点】重要なのは「運用定着」と「組織文化の醸成」
顧客ランク分けの仕組みを導入しても、それが現場で使われなければ意味がありません。多くの企業が直面する課題は、システムの導入そのものではなく、その後の「運用定着」です。
運用を定着させるためには、以下の点が重要です。
現場のメリットの明確化:営業担当者が「このランク分けを使うことで、自分の営業活動が効率化され、成果につながる」と実感できるような設計と情報提供が必要です。
継続的なトレーニングとサポート:ツールの使い方やランクの解釈について、継続的なサポートを提供します。
データドリブンな組織文化の醸成:勘や経験だけでなく、データに基づいて意思決定を行う文化を組織全体で醸成していくことが、長期的な成功につながります。
Sells upでは、ツールの設定や分析手法の提供だけでなく、貴社の組織体制やビジネスプロセスに合わせた運用設計と、現場への定着支援までを一貫してサポートし、データ活用が組織文化として根付くことを目指します。
まとめ
顧客ランク分けは、BtoB企業が限られたリソースを最適配分し、売上成長と営業効率化を実現するための重要な取り組みです。属人化した営業から脱却し、データに基づいた客観的な基準で顧客の優先順位を明確にすることが、その最初のステップとなります。
デシル分析やRFM分析といった基本的な手法を理解した上で、BtoB特有の「企業属性」「取引実績」「エンゲージメント」を組み合わせた複合的な指標を用いることが有効です。そして、その運用にはSFA/MAツールの活用が不可欠です。ツールを活用することで、効率的かつ動的なランク管理が実現し、ランク変動をトリガーとしたタイムリーなアプローチが可能になります。
導入にあたっては、目的の明確化、データ整備、そして部門間の連携を意識したワークフロー設計が成功のポイントです。最初から完璧を目指さず、運用しながら継続的に改善を重ねる姿勢で、顧客ランク分けを貴社の成長を支える仕組みとして活用してください。
MAツールの導入・活用の相談はSells upへ。
MAツールの導入や、導入後の成果最大化に課題をお持ちでしたら、ぜひSells upにご相談ください。50社以上の導入・活用を支援してきた担当者が貴社の状況・目標に向き合い、最適なツールの導入プラン / 統計知識を用いた活用プラン描き、戦略策定から実装 / 実行 / 効果測定までをご支援いたします。
CONTACT







