リードナーチャリング成功事例14選|BtoB企業の課題を解決した施策と成果を解説
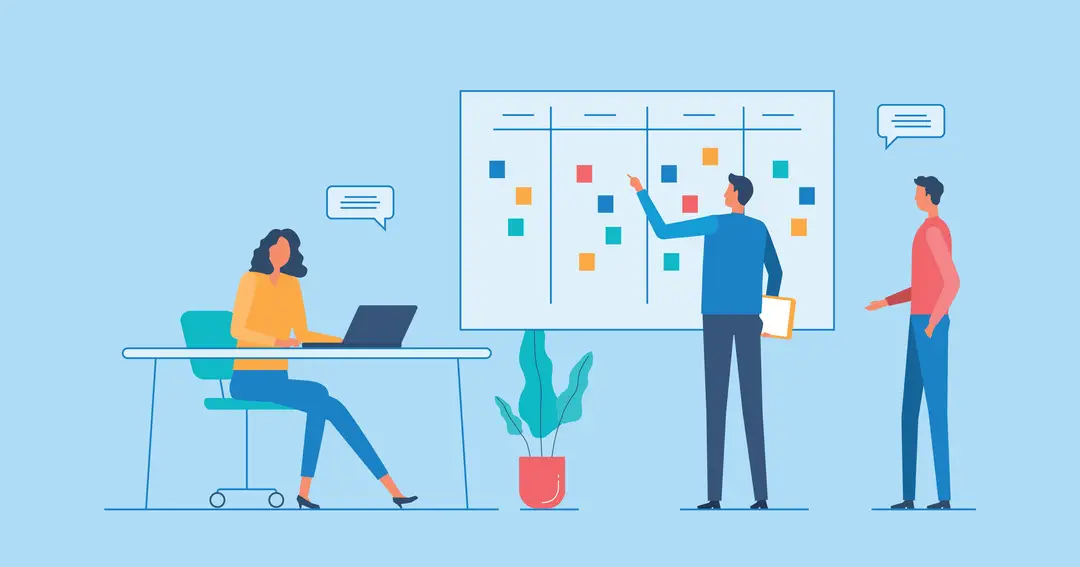
MAツールの導入・活用の相談はSells upへ。
MAツールの導入や、導入後の成果最大化に課題をお持ちでしたら、ぜひSells upにご相談ください。50社以上の導入・活用を支援してきた担当者が貴社の状況・目標に向き合い、最適なツールの導入プラン / 統計知識を用いた活用プラン描き、戦略策定から実装 / 実行 / 効果測定までをご支援いたします。
コンテンツマーケティング(WP・ブログ等)
「Web広告や展示会でリード(見込み顧客)は獲得できているのに、商談に繋がらない」
「営業部門からは『もっと質の高いリードが欲しい』と言われるが、具体的に何をすべきかわからない」
「MAツールを導入したものの、メルマガの一斉配信しかできていない」
BtoB企業のマーケティング担当者であれば、このような課題に直面した経験があるのではないでしょうか。
獲得したリードに対し、中長期的に適切なコミュニケーションを行い、購買意欲を高めていく「リードナーチャリング」は、検討期間が長いBtoBビジネスにおいて、事業成長に不可欠な取り組みです。
しかし、概念は理解していても、「自社に最適な施策は何か?」「他社は具体的にどのような成果を上げているのか?」「導入のROI(投資対効果)をどう説明すればよいか?」という疑問は尽きません。
本記事では、日本国内のBtoB企業を中心に、リードナーチャリングの成功事例14選を厳選して紹介します。単なる事例紹介に留まらず、各社が抱えていた課題、実行した具体的な施策、そして得られた成果という一連のプロセスを深掘りします。
さらに、多くの企業が陥りがちな失敗パターンとその解決策、自社に最適な施策を選ぶための比較フレームワーク、そして成果に繋げるためのKPI設定や部門連携の具体論までを解説します。
リードナーチャリングとは?BtoB企業における必要性とその課題
リードナーチャリングとは、獲得したリードに対し、段階的に適切な情報提供やコミュニケーションを行い、購買意欲を高めて商談や受注へとつなげる活動です。
BtoBビジネスでは、顧客は営業担当者に接触する前に、Web上で情報収集を行い、ある程度の比較検討を終えているケースが増加しています。また、意思決定に関わる人数が多く、検討期間が長期化しやすい特徴があります。
そのため、早期の段階からリードと接点を持ち、信頼関係を構築しながら、自社の製品やサービスが課題解決にどう貢献できるかを継続的に伝える必要があります。営業担当者が全てのリードをフォローすることはリソース的に困難であり、マーケティング部門が体系的に「リードの質」を高める取り組みが重要となります。
近年、MA(マーケティングオートメーション)ツールの導入が進みましたが、多くの企業が以下のような課題に直面しています。
獲得したリードの多くが休眠化してしまっている
MAツールを導入したが、機能を使いこなせていない(メルマガ配信ツール化している)
営業部門が求める「質の高いリード」の定義が曖昧で、連携がうまくいかない
施策の投資対効果(ROI)を測定・説明できていない
これらの課題を解決するには、他社の成功事例から具体的な施策とその背景にある考え方を学び、自社の状況に合わせて最適なナーチャリング施策を設計することが近道です。
BtoBリードナーチャリングの主な施策分類
リードナーチャリングの手法は多岐にわたりますが、BtoB企業で成果を上げている主な施策は以下の6つに分類できます。自社のリソースやリードの状況に合わせて、これらを組み合わせて実施することが一般的です。
メールマーケティング:最も基本的で費用対効果の高い手法。セグメント配信やシナリオ配信で個別最適化を図ります。
コンテンツマーケティング:ホワイトペーパー、導入事例、オウンドメディア記事など。リードの課題解決に役立つ情報を提供し、信頼関係を構築します。
インサイドセールス:電話やメールで非対面のコミュニケーションを行い、リードの課題をヒアリングし、商談機会を創出します。
セミナー・ウェビナー:製品やノウハウを体系的に伝え、リードとの接点を深めます。参加後のフォローアップが重要です。
MAツール・CRM/SFA連携:施策実行の基盤。リード情報の管理、スコアリング、施策の自動化、営業部門への情報連携を担います。
SNS・広告活用:休眠リードの再活性化や、特定のセグメントへのピンポイントなアプローチに活用されます。
次のセクションから、これらの施策ごとの具体的な成功事例を見ていきましょう。
【施策別】BtoBリードナーチャリング成功事例14選
ここからは、具体的な施策別に14社の成功事例を紹介します。各社の「課題」「施策」「成果」を比較し、貴社で取り組む際の参考にしてください。
メールマーケティング施策の事例(3選)
メールマーケティングは、リードナーチャリングの基本となる施策です。成功のポイントは、全てのリードに同じ内容を送るのではなく、リードの属性や検討段階に応じて「誰に」「何を」「どのタイミングで」送るかを設計することにあります。
事例1:株式会社シンフィールド|メールの目的を明確に分け、アポイント率を向上
課題:展示会やセミナーで獲得した名刺リストを十分に活用できておらず、営業活動の成果に繋がっていなかった。フォローの基準も曖昧だった。
施策
メールの目的を2種類に分類。2週に1回配信するノウハウ中心の「お役立ちメール」と、営業要素を含んだ「引き上げメール」を使い分けて配信。
「引き上げメール」内のURLクリックなど、リードの具体的な反応をトリガーとして設定し、インサイドセールスが電話フォローを実施。
成果:アポイント率が10~15%に上昇し、その後の成約率も向上。リスト活用の効率化と営業コストの抑制を両立させた。
出典:【リードナーチャリング事例】メールマーケティングに「ちょい足し」で成果をあげるシンフィールドの取り組み|メルラボ
事例2:CARTA COMMUNICATIONS|ターゲット別のコンテンツ設計で開封率・クリック率が改善
課題:展示会などで集めたリードが商談に結びつかず、リードごとの温度感を把握しきれていなかった。画一的なアプローチになっていた。
施策
リードを業種や検討段階(情報収集中、比較検討中など)でセグメント化し、それぞれの関心に応じたコンテンツ(事例紹介、ノウハウ資料など)をメールで配信。
MAツールを活用し、メールの開封・クリックデータをもとにリードのスコアリングを実施。一定のスコアを超えたリードを抽出。
成果:開封率・クリック率が大幅に改善し、ホットリード(購買意欲の高いリード)の抽出精度が向上。営業部門への引き継ぎがスムーズになった。
出典:株式会社CARTA COMMUNICATIONS 導入事例|シナジーマーケティング株式会社
事例3:ユミルリンク株式会社|定期的な情報提供でセミナー参加率とリードの再活性化に成功
課題:セミナーへの集客が安定せず、既存リードとの定期的な接点が不足し、休眠化が進んでいた。
施策
自社のメール配信システムを活用し、セミナー案内だけでなく、業界の最新ニュースや調査レポートなどを定期的に配信。
過去のセミナー参加者に対しても継続的に情報提供を行い、リピート参加を促進。
成果:セミナー参加率が上昇し、関連するホワイトペーパーのダウンロード数も増加。休眠していたリードの再活性化に繋がった。
参考:SNSより確実?メールマーケティングの今をユミルリンク大粒来氏が語る|LISKUL
【Sells upの視点】メール施策は「配信リストの質」が成果を左右する
メールマーケティングの成果は、配信コンテンツの内容だけでなく、「配信リストの質」に大きく依存します。MAツール内に古い情報や重複したデータが蓄積されていると、せっかくの施策も効果が薄れてしまいます。成功企業は、定期的なデータクレンジング(名寄せ・情報更新)を行い、常に最新のリード情報を基にセグメンテーションを行っています。メール施策を見直す際は、まず自社のリードデータが正しく管理されているかを確認することが重要です。
コンテンツマーケティング施策の事例(2選)
コンテンツマーケティングは、リードの課題解決や情報収集を支援することで、自社への信頼感を醸成し、中長期的な関係を構築する手法です。BtoBにおいては、製品の宣伝ばかりではなく、専門知識やノウハウを提供することがポイントとなります。
事例4:株式会社マックスプロデュース|専門ノウハウの提供で確度の高い新規リードを獲得
課題:新規顧客開拓において、ターゲットであるイベント開催の意思決定者に効率的にリーチできていなかった。
施策
自社オウンドメディアで、イベント運営に関する具体的なノウハウや過去の事例を体系的に発信。
会場レイアウト例やチェックリストなど、実務で使える資料をホワイトペーパーとして作成。ダウンロード時にリード情報を取得する導線を設置。
成果:資料ダウンロードを通じて、具体的な課題を持った新規リードを獲得。営業部門が確度の高いリードへ効率的にアプローチできる体制を構築できた。
出典:CMS×オウンドメディア活用成功事例|「MAX広場」株式会社マックスプロデュース様‐Knowus
事例5:株式会社クラシコム|世界観を伝えるコンテンツでブランドファンを育成
課題:ブランドの認知度はあるものの、すぐに購買につながるリードだけでなく、中長期的なファン育成が必要だった。
施策
オウンドメディア(北欧、暮らしの道具店)を中心に、製品紹介に留まらない生活提案型のコンテンツを展開。
SNSやアプリも連携させ、一貫した世界観でユーザーとのエンゲージメントを強化。
成果:月間1,500万PVを超えるメディアに成長。コンテンツを通じてブランドへのロイヤリティが高まり、結果としてリードの質とLTV(顧客生涯価値)が向上した。BtoBにおいても、自社の専門性やビジョンを伝えるコンテンツは有効です。
参考:「北欧、暮らしの道具店」が生まれるまで。世界観の作り方、SNS運用の秘訣‐SELECK
【Sells upの視点】コンテンツは「量」より「資産性」を重視する
リードナーチャリングにおけるコンテンツは、一時的な集客だけでなく、長期的にリードを惹きつけ、育成する「資産」として捉えるべきです。成功企業は、ペルソナが抱える本質的な課題に応える質の高いコンテンツ(例えば、体系的なノウハウをまとめたホワイトペーパーや、具体的な成果を示す導入事例)を作成し、それをメールやウェビナーなど他の施策と連携させて活用しています。コンテンツを点で作るのではなく、カスタマージャーニー全体を俯瞰し、どの検討段階でどのコンテンツが必要かを戦略レイヤーで設計することが重要です。
インサイドセールス施策の事例(3選)
インサイドセールスは、マーケティングと営業の間に立ち、リードの質を高める(クオリフィケーション)重要な役割を担います。MAツールで抽出したリードに対し、電話やメールでアプローチし、課題の深掘りや予算・時期(BANT情報)のヒアリングを行います。
事例6:日本電気株式会社(NEC)|部門間の連携フロー構築で商談化率を向上
課題:リード数が膨大で、営業部門が全てのリードを十分にフォローしきれず、機会損失が発生。商談化率が伸び悩んでいた。
施策
インサイドセールス部門を新設。MAツールを活用し、リードの行動履歴から検討度を可視化(スコアリング)。
マーケティング、インサイドセールス、フィールドセールス(外勤営業)の3部門で連携し、一定の基準を満たしたホットリードのみを営業部門へ引き渡すフローを構築。
成果:リード育成の効率が格段に改善し、商談化率が向上。営業部門は確度の高い商談に集中できるようになった。
参考:NECが挑戦する営業・マーケティングの融合とデジタルシフト 2年間の取り組みで実感する変化とは‐MarkeZine
事例7:株式会社マイナビ|ホットリードの定義を明確化し、商談数が1.5倍に増加
課題:マーケティング部門と営業部門でリードの評価基準が異なり、「質が低い」「フォローしてくれない」といった対立構造が生まれていた。また、一度失注したリードが放置されていた。
施策
インサイドセールス部門を中心に、どのような状態のリードを「ホットリード」とするかの定義を部門間で明確化し、共通認識を持った。
一度失注したリードや、商談に至らなかったリードを再度育成する「リードリサイクル」の仕組みを導入。
成果:部門間の連携がスムーズになり、商談数が前期比1.5倍に増加。既存リードの再活用も進んだ。
出典:インサイドセールス導入で新規獲得率は3.5倍!マイナビ流「急がば回れ」の営業改革事例|SalesZine
事例8:株式会社マネーフォワード|事前ヒアリングの自動化で営業効率を向上
課題:インサイドセールスによる初回ヒアリングに時間がかかり、対応できるリード数に限界があった。営業負荷も高かった。
施策
Webサイト上に事前アンケートフォームを設置し、商談前に知りたい基本的なヒアリング内容(課題感、予算感など)を自動で取得する仕組みを導入。
インサイドセールスのトークスクリプトやヒアリング項目を標準化し、活動を効率化。
成果:1件あたりのヒアリング時間を大幅に短縮。顧客の課題を事前に把握できるため、商談の質も向上した。
参考:全員が未経験から立ち上げ!受注率2.5倍、MFクラウド経費のインサイドセールスとは‐SELECK
セミナー・ウェビナー施策の事例(3選)
セミナーやウェビナーは、一度に多くのリードに対して体系的な情報を提供できる効率的な手法です。特にウェビナーは場所の制約がなく、参加ハードルが低いため、広く活用されています。開催すること自体が目的化しないよう、開催前後のフォロー設計が成果を分けます。
事例9:SATORI株式会社|ウェビナーとアーカイブ配信の組み合わせで商談件数が増加
課題:対面セミナーでは参加率に限界があり、参加後のフォローも担当者のスキルに依存し属人化していた。
施策
リアルタイムのウェビナー開催に加え、参加できなかったリード向けにアーカイブ配信を実施し、参加機会を最大化。
MAツールで参加者の視聴データ(視聴時間、離脱箇所など)を管理し、関心度合いに応じたフォローアップを自動化。
成果:参加率・視聴時間が伸び、ウェビナー経由での商談件数が増加。フォローの抜け漏れも防止できた。
出典:疑似ライブ配信でウェビナーを効率化ネクプロ×「SATORI」で見込み顧客を育成|ネクプロ
事例10:株式会社東京商工リサーチ|セミナー運営と参加者管理の一元化でフォロー精度が向上
課題:セミナー参加者の情報管理がExcelなどで煩雑になっており、セミナー後の追客(フォロー)の精度が低かった。
施策
セミナー管理ツールとMAツールを連携させ、申し込みから参加後までの運営と参加者管理を一元化。
セミナー後のアンケート回答内容に基づき、リード育成シナリオを自動で分岐させた。
成果:運営効率が向上し、参加者への対応が迅速化。データに基づいた的確なフォローが可能になった。
出典:MAツールの刷新でメルマガの開封率を23%向上ウェビナーの効率的な運用も実現|ソフトバンク
MAツール・CRM連携施策の事例(2選)
MAツールやCRM/SFAは、リードナーチャリングを効率的かつ効果的に実行するための基盤です。これらのツールを連携させ、リード情報を一元管理し、データに基づいて施策を自動化することが成功のポイントです。
事例11:Oktopost社|MAツールによる高度なセグメント配信と即時フォロー
課題:多様なリードが存在し、それぞれの検討段階に応じた最適なアプローチを行うことが難しかった。
施策
MAツールでリードの状況(例:トライアル利用中、利用終了後など)を細かく分類し、それぞれに最適化されたコンテンツを配信。
ホワイトペーパーのダウンロードや料金ページの閲覧といった具体的なアクションをトリガーに、チャットやインサイドセールスが即座にフォローする体制を構築。
成果:リードの反応に対するレスポンス速度が向上し、顧客満足度と受注率が改善した。
出典:B2B lead nurturing strategies for dummies‐Oktopost
事例12:株式会社ランドネット|顧客情報の一元管理とスコアリング自動化で面談申込数が増加
課題:Web広告、ポータルサイトなど集客媒体ごとにリード管理が分断されており、顧客一人ひとりに最適なアプローチができていなかった。
施策
MAツールを導入し、全媒体から得られるリード情報を一元的に管理するデータベースを構築。
リードの行動に基づいたスコアリングや、属性に基づいたセグメント配信を自動化し、最適なタイミングでのアプローチを実現。
成果:顧客ごとの状況に応じたコミュニケーションが可能になり、信頼構築が促進。結果として面談申込数が増加した。
SNS・広告活用施策の事例(2選)
SNSやWeb広告は、新規リード獲得だけでなく、既存リードとの関係維持や休眠リードの掘り起こしにも活用できます。他の施策と組み合わせることで、ナーチャリング効果を高めることが可能です。
事例13:ランスタッド株式会社|LINE活用でコミュニケーション速度が向上し、返信率が80%に
課題:求職者(リード)への連絡手段がメールや電話中心で、返信率が低迷(約20%)。コミュニケーションが滞り、休眠会員が増加していた。
施策
求職者との主要な連絡手段を、より手軽で開封率の高いLINEに変更し、タイムリーなやり取りを実現。
LINE上でのコミュニケーションを通じて状況を把握し、案件紹介のタイミングを最適化。
成果:返信率が80%へと劇的に上昇。コミュニケーション速度が上がり、案件マッチング率も改善した。
事例14:Sansan株式会社|Facebook広告を活用した休眠リードの掘り起こし
課題:過去に接点があったものの、長期間アプローチできていない休眠リードが大量に存在していた。メール配信だけでは反応が得られなかった。
施策
MAツールに蓄積された休眠リードのリスト(メールアドレス)を抽出し、Facebook広告のカスタムオーディエンス機能を利用してターゲティング配信。
休眠リードが関心を持ちそうな最新のホワイトペーパーやセミナー情報を広告で訴求し、再度の接点獲得を目指した。
成果:メール配信だけでは反応しなかった休眠リードを効率的に掘り起こし、新たな商談機会を創出できた。
参考:休眠リードを案件化!Sansanが明かす、Facebook「リード獲得広告」成果を出す3つの秘訣|MarkeZine
リードナーチャリングでよくある失敗パターンと解決策
多くの企業がリードナーチャリングに取り組む一方で、期待した成果が得られないケースも少なくありません。ここでは、成功事例の裏側にある、よくある失敗パターンとその解決策を解説します。これは、貴社が同じ過ちを犯さないための重要な情報です。
失敗パターン1:MAツールを導入しただけで満足してしまう
最も多い失敗が、MAツールを導入したものの、機能を十分に活用できていないケースです。「高機能なツールさえあれば何とかなる」と考えがちですが、ツールはあくまで手段です。戦略や運用体制が整っていない状態でツールだけを導入しても、結局はメルマガの一斉配信程度しか使われず、成果には繋がりません。
解決策
MAツール導入の目的(例:商談化率を〇%向上させる)を明確にする。
自社のリード情報管理の現状を把握し、データ整備から着手する。
専任の担当者またはチームを配置し、運用体制を構築する。スモールスタートで成功体験を積むことも有効です。
失敗パターン2:提供するコンテンツが製品の宣伝ばかりになる
リードナーチャリングの目的は、リードとの信頼関係を構築することです。しかし、自社製品の機能紹介やキャンペーン情報など、宣伝色の強いコンテンツばかり提供していると、リードは離れてしまいます。リードはまず自社の課題を解決するための情報を求めている、という視点が重要です。
解決策
ペルソナ(ターゲット顧客像)とカスタマージャーニー(購買プロセス)を明確に定義する。
各検討段階(情報収集中、課題認識、比較検討など)において、リードが求めている情報(ノウハウ、業界動向、事例など)を提供する。
製品紹介は、リードの購買意欲が高まった段階で、課題解決の手段として提示する。
失敗パターン3:マーケティングと営業の連携が取れていない
マーケティング部門が懸命にリードを育成しても、営業部門との連携がうまくいっていないと成果は出ません。「マーケティングは質の低いリードばかり渡してくる」「営業はせっかく渡したリードをフォローしてくれない」といった対立構造は、多くの企業で見られます。
解決策
「どのような状態になったらホットリードとするか」の定義を、部門間で明確に言語化し、共通認識を持つ。
SLA(Service Level Agreement:サービス品質保証)を締結し、リード引き渡し後の対応ルール(例:〇時間以内に初回連絡する)を定める。
CRM/SFAを活用し、リード情報や商談の進捗状況をリアルタイムで共有する。
定期的なミーティングを開催し、施策の成果や改善点(特に失注理由のフィードバック)を共有する文化を醸成する。
【Sells upの視点】失敗の根本原因は「データ分断」にあることが多い
上記のような失敗パターンの根本には、多くの場合「データの分断」が潜んでいます。顧客接点が多様化する中、マーケティング、インサイドセールス、フィールドセールスがそれぞれ異なるツールやExcelで情報を管理していると、顧客の状況を正しく把握できず、連携もうまくいきません。リードナーチャリングを成功させるためには、MA、CRM/SFAを連携させ、リード獲得から受注後までの一連のデータを一元管理する基盤構築が不可欠です。この基盤があって初めて、データに基づいた的確な意思決定と部門横断の連携が可能になります。
自社に最適な施策を見つけるための比較と選定フロー
ここまで多くの事例や施策を見てきましたが、「では、自社は何から始めるべきか?」と悩む方も多いでしょう。ここでは、各施策の特徴を比較し、自社に合った施策を選定するためのフローを解説します。
主要なリードナーチャリング施策の比較フレームワーク
各施策にはメリット・デメリットがあり、必要なリソースや適した状況も異なります。以下の表を参考に、貴社の現状と照らし合わせてみてください。
施策 | メリット | デメリット・注意点 | 必要なリソース(工数・費用) | 適した状況(例) |
|---|---|---|---|---|
| メールマーケティング | ・低コストで開始できる | ・開封率が低下傾向にある | 低~中 | ・リード数が一定数ある |
コンテンツマーケティング(WP・ブログ等) | ・信頼関係を構築できる | ・成果が出るまでに時間がかかる | 中~高 | ・専門性の高い商材を扱っている |
| インサイドセールス | ・リードの状況を直接ヒアリングできる | ・人件費がかかる | 高 | ・高単価な商材を扱っている |
| セミナー・ウェビナー | ・短時間で理解を深められる | ・企画・集客 | 中~高 | ・複雑な商材を扱っている |
自社に合った施策を選定するステップ
以下のステップで検討を進めることで、貴社に最適な施策を見つけることができます。
Step.1:現状の課題と目標を明確にする
まずは、自社のリード管理の現状を把握し、「リード数が不足しているのか」「リードの質が低いのか」「休眠リードが多いのか」といった具体的な課題を特定します。その上で、リードナーチャリングによって達成したい目標(KGI)を設定します。
Step.2:ターゲットと購買プロセスを定義する
誰をターゲットとし(ペルソナ)、そのターゲットがどのようなプロセスで製品・サービスを購買するのか(カスタマージャーニー)を定義します。これにより、どの段階でどのような情報提供が必要かが見えてきます。
Step.3:利用可能なリソースを確認する
施策実行に必要な予算、人材(担当者のスキルや工数)、利用可能なツール(MA、CRMなど)を確認します。リソースが限られている場合は、優先順位をつけて段階的に取り組む計画を立てます。
Step.4:施策を選定し、KPIを設定する
Step.1~3を踏まえ、比較表を参考にしながら自社に最も効果的と思われる施策を選定します。そして、施策ごとの効果を測定するための指標(KPI)を設定します。
成功事例から学ぶ、成果を出すための重要ポイント
最後に、今回紹介した成功事例に共通する、リードナーチャリングで成果を出すための重要なポイントをまとめます。これらは、貴社が施策を実行する上での具体的な指針となり、また社内で施策導入を説明する際の根拠としても活用できます。
ポイント1:データに基づいたリードの可視化とスコアリング
成功企業は、MAツールやCRMを活用し、リードの属性情報(業種、役職など)と行動情報(Webアクセス履歴、メール開封、資料ダウンロードなど)を一元管理しています。そして、これらのデータに基づいてリードの状況を可視化しています。
特に重要なのが「スコアリング」です。リードの行動や属性に対して点数を付け、合計点によって購買意欲の度合いを客観的に評価します。これにより、今アプローチすべきホットリードを効率的に抽出し、営業部門へ引き渡すことが可能になります。
ポイント2:マーケティングと営業の連携を具体化するルール(SLA)の設計
多くの記事が「連携が重要」と述べるに留まっていますが、成功企業はそれを具体的なルールとして仕組み化しています。その代表例がSLA(Service Level Agreement)の締結です。こでは実行レベルのノウハウを提示します。
SLA設定項目の具体例
ホットリードの定義:どのような条件(スコア〇点以上、特定のページを閲覧、BANT情報が揃っているなど)を満たしたリードを営業に引き渡すか。
引き渡し後の対応ルール:リードを受け取ってから〇時間以内に初回連絡を行う、〇回以上連絡しても繋がらなかった場合はマーケティングに差し戻す(リサイクルする)、など。
情報共有とフィードバックの仕組み:商談の進捗状況や失注理由は必ずCRMに入力し、マーケティング部門へフィードバックする。失注理由のフィードバックをどう仕組み化するかが重要です。
このように具体的なルールを定めることで、連携の属人化を防ぎ、組織全体で成果を追求することができます。
ポイント3:事業貢献度を測るKPI設計と継続的な改善サイクル
リードナーチャリングの成果を正しく評価し、社内での評価を得るためには、適切なKPI設定が不可欠です。メールの開封率やクリック率といった中間指標だけでなく、最終的な事業貢献度を測る指標を設定することが重要です。
成果に繋がるKPI設定の具体例
KGI(最終目標):受注数、受注金額、LTV(顧客生涯価値)
KPI(中間指標):
ホットリード創出数
MQL(Marketing Qualified Lead:マーケティングが創出した質の高いリード)数
SQL(Sales Qualified Lead:営業が商談対象と判断したリード)数
商談化率、案件化率、受注率
休眠リードからの再活性化数
これらのKPIを定期的に計測し、目標とのギャップを分析し、施策の改善を繰り返す(PDCAサイクルを回す)体制を構築することが、継続的な成果創出に繋がります。
よくある質問(FAQ)
Q1.リードナーチャリングを始める際、最初に取り組むべきことは何ですか?
A.まずは自社が保有しているリード情報を整理し、現状の課題を明確にすることが最初のステップです。MAツールやCRMを活用してリードの属性や過去の行動履歴を把握し、どの層のリードが休眠化しているのか、どのプロセスで離脱が多いのかを分析してください。その上で、ターゲットとなるペルソナやカスタマージャーニーを再設定し、効果測定可能なKPIを設計することが推奨されます。
Q2.MAツールを導入しても成果が出ない場合、何を見直すべきですか?
A.MAツールの導入自体が目的化している可能性があります。まずは運用体制、提供しているコンテンツの質、スコアリング基準の妥当性、そして営業部門との連携体制などを総合的に見直しましょう。特に、部門間でホットリードの定義や引き渡し後のルール(SLA)が明確になっているかを確認し、データに基づいてPDCAサイクルを回すことが成果向上のポイントです。
Q3.休眠リードを再活性化するための有効な施策は何ですか?
A.休眠リードに対しては、まずは相手の負担にならない形で有益な情報を提供することが有効です。例えば、最新の業界動向をまとめたレポート、導入事例、ウェビナーの案内などが挙げられます。また、Web広告(リターゲティング広告やカスタムオーディエンス広告)を活用し、休眠リードに的を絞ってアプローチする方法もあります。重要なのは、再度ホットリード化したタイミングを見逃さず、適切なアプローチができる体制を整えておくことです。
Q4.リードナーチャリングの成果が出るまでにはどれくらいの期間がかかりますか?
A.商材の単価や検討期間によって異なりますが、一般的にBtoBビジネスでは、施策を開始してから目に見える成果(受注)が出るまでには半年から1年程度かかると言われています。リードナーチャリングは中長期的な取り組みであるため、短期的な成果だけでなく、商談化率やホットリード創出数といった中間KPIを追いながら、継続的に改善を進めることが重要です。
まとめ
リードナーチャリングは、マーケティングと営業が一体となり、データに基づいてリードの購買意欲を高め、商談・受注へとつなげるための重要なプロセスです。
本記事で紹介した14社の成功事例からは、以下の共通点が見て取れます。
自社の課題を明確にし、目的に合ったKPIを設計している
MAツール・CRM/SFAを活用し、リード情報を一元管理・可視化している
部門間の連携ルール(SLA)を定め、ホットリードの定義を明確化している
リードの検討段階に応じたコンテンツを継続的に提供している
データに基づいて施策を評価し、PDCAサイクルを徹底している
成功事例や失敗パターン、そして施策選定のフレームワークを参考に、貴社の状況に合った施策を選定し、段階的な改善を積み重ねることで、リードナーチャリングのROI向上と営業成果の創出を目指してください。
MAツールの導入・活用の相談はSells upへ。
MAツールの導入や、導入後の成果最大化に課題をお持ちでしたら、ぜひSells upにご相談ください。50社以上の導入・活用を支援してきた担当者が貴社の状況・目標に向き合い、最適なツールの導入プラン / 統計知識を用いた活用プラン描き、戦略策定から実装 / 実行 / 効果測定までをご支援いたします。
CONTACT







