MAツールの使い方|成果を出すシナリオと失敗しないための導入準備
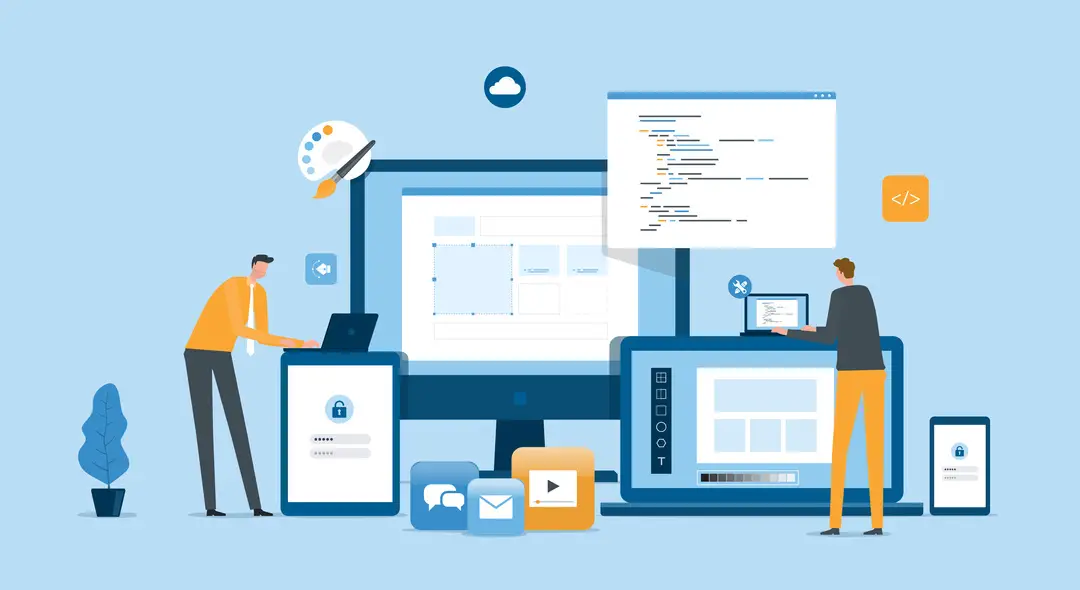
MAツールの導入・活用の相談はSells upへ。
MAツールの導入や、導入後の成果最大化に課題をお持ちでしたら、ぜひSells upにご相談ください。50社以上の導入・活用を支援してきた担当者が貴社の状況・目標に向き合い、最適なツールの導入プラン / 統計知識を用いた活用プラン描き、戦略策定から実装 / 実行 / 効果測定までをご支援いたします。
MAツールとは?まずは基本の「できること」を理解する
MA(マーケティングオートメーション)ツールの導入を検討する際、多くの担当者がその多機能性に期待を寄せます。しかし、その本質を理解しないままでは、無駄な投資になりかねません。まずはMAツールが何を解決するためのツールなのか、その基本から押さえましょう。
そもそもMA(マーケティングオートメーション)ツールとは
MAツールとは、これまで手作業で行っていたマーケティング活動を自動化・効率化するためのシステムです。具体的には、Webサイトなどから獲得した見込み顧客(リード)の情報を一元管理し、それぞれの興味・関心度に合わせて継続的なアプローチを行い、最終的に営業部門が商談しやすい状態へと育成することを目的とします。
Excelでのリスト管理や、手動での一斉メール配信といった属人的な業務から脱却し、データに基づいた効率的なマーケティング活動を実現する。それがMAツールの基本的な役割です。
MAツールが担う3つの主要な役割
MAツールの活動は、大きく3つの役割に分解できます。この流れを理解することが、効果的な使い方への最初のステップです。
役割1:見込み顧客の獲得(リードジェネレーション)
MAツールは、Webサイトのフォームやランディングページ、セミナー、広告などさまざまなチャネルで見込み顧客(リード)を獲得します。これらの情報を自動で蓄積し、Excel管理から脱却できる点は中小規模のマーケティング組織にとって大きなメリットになります。
役割2:見込み顧客の育成(リードナーチャリング)
獲得した見込み顧客が、すぐに製品を購入してくれるわけではありません。MAツールは、顧客のWebサイト閲覧履歴やメールへの反応といった行動データを基に、「どの情報に興味があるのか」を把握します。そして、その興味に合わせたお役立ち情報や事例紹介などを、適切なタイミングで自動配信し、徐々に購買意欲を高めていきます。
役割3:見込み顧客の選別(リードクオリフィケーション)
すべてのリードが営業案件になるわけではありません。MAツールは、資料請求やWebサイトの閲覧などの行動を点数化(スコアリング)し、営業部門が優先すべき「温度感の高いリード」を可視化します。営業リソースを集中投下できるため、成約率向上につながります。
SFAやCRMとの違いは「担当領域」
MAツールとよく比較されるのが、SFA(営業支援システム)やCRM(顧客関係管理システム)です。これらの違いは、顧客との関係性における担当領域にあります。
MAツール:匿名顧客から見込み顧客になり、商談に至るまでの「マーケティング領域」を担当
SFA:商談発生から受注までの「営業領域」を担当
CRM:受注後の既存顧客との関係維持・向上を担う「カスタマーサクセス領域」を担当
重要なのは、これらを分断して活用するのではなく、連携させることが重要であるという点です。例えば、MAで育成した質の高いリード情報をSFAに連携すれば、営業担当は顧客の関心事を事前に把握した上で商談に臨めます。このデータ連携こそが、部門間の壁を越えたスムーズな顧客対応を実現します。
【Sells upの視点】ツール導入は目的ではなく、あくまで営業成果向上のための手段
MAツールの導入を検討する際、「どのツールが高機能か」という議論に終始してしまうケースは少なくありません。しかし、忘れてはならないのは、ツール導入はゴールではないということです。ツールを導入する目的は、MAツールという仕組みを使って「営業部門の商談化率を上げる」「安定的に質の高いリードを供給する」といった事業成果に貢献することにあります。データに基づき、マーケティング活動を営業成果に反映させるための手段としてMAツールを捉える視点が不可欠です。
導入で失敗しないために。MAツールを使い始める前の必須条件
「MAツールを導入したものの、高価なメルマガ配信ツールになっている」。
これは、導入に失敗した企業から最も多く聞かれる声です。なぜ多くの企業がMAツールを使いこなせないのでしょうか。その原因は、ツール導入前の「準備不足」にあります。
なぜ多くの企業がMAツールを使いこなせないのか?
失敗の背景には、共通するいくつかの課題が存在します。
目的の欠如:「競合が導入したから」といった曖昧な理由で始め、具体的な目標がない。
リソース不足:兼任担当者一人に任せきりで、シナリオ設計やコンテンツ作成の時間が確保できない。
コンテンツ不足:見込み顧客に提供できるお役立ち資料やブログ記事が圧倒的に足りない。
リード不足:育成対象となる見込み顧客の母数が少なく、自動化の恩恵を受けられない。
営業部門との連携が脆弱:マーケティング部門だけで導入を進め、営業部門の協力が得られない。
これらの課題を放置したまま導入に踏み切っても、期待した成果は得られません。
準備は万全?導入前に確認すべき5つのチェックリスト
MAツールの導入を成功させるためには、以下の5つの条件が整っているか、事前に必ず確認してください。
条件1:成果につながる十分な見込み顧客(リード)数があるか
MAツールは、ある程度のリード母数があって初めて効果を発揮します。目安として、最低でも数千件以上のリードリストがなければ、セグメンテーションやスコアリングの効果は限定的です。もしリード数が不足している場合は、まずWeb広告やSEO対策でリード獲得に注力することが先決です。
もっと言うと、「3年前に失注して、それ以降なにも連絡していないリード」のような、「非アクティブリード」が何万件あったとしても、なんの意味もありません。
あくまでも「いまMAツールにインポートして、メール開封やwebページ閲覧が発生する」と考えられるアクティブなリードが数千件以上あることが望ましいです。
条件2:見込み顧客を惹きつけるコンテンツは揃っているか
MAツールは、あくまでコンテンツを届けるための「器」です。中に入れるコンテンツ(ブログ記事、ホワイトペーパー、導入事例など)がなければ、顧客を育成することはできません。導入前に、顧客の課題解決に繋がるコンテンツを継続的に制作できる体制があるか、見直しましょう。
条件3:MAツールで達成したい「具体的な目標」が設定されているか
「業務を効率化したい」といった漠然とした目標では、施策の評価ができません。「半年後に、MA経由の商談化率を現状の1.5倍にする」「休眠顧客から毎月10件の有効商談を創出する」など、誰が見ても達成度がわかる具体的な数値目標(KPI)を設定することが非常に重要です。
条件4:ツールを運用するための人的リソースを確保できるか
MAツールは、シナリオ設計、コンテンツ企画、効果測定など、思考を要する業務が必ず発生します。これらの業務を誰が主導するのか、といった担当者を明確に定め、最低でも週に半日~1日はMA運用のための時間を確保できるか、を事前に確認しておく必要があります。
条件5:営業部門との連携体制を構築できるか
MAツールの最終的な目的は、営業部門の成果向上への貢献です。そのためには、「どんな状態のリードを」「どのタイミングで」営業に引き渡すのか、部門間でルールを定めておく必要があります。
週次での定例会議を設定するなど、情報共有とフィードバックの仕組みをあらかじめ設計しておきましょう。
【Sells upの視点】MA導入の成否は、ツール選定以前の「準備」で9割決まる
私たちは多くの企業のMA導入・活用をご支援してきましたが、どれだけ優れたMAツールを選定しても、導入前の準備が不十分な場合は、どれだけテクニカルな設定を行ったとて成果にはつながりません。リードやコンテンツ、目標、体制、営業連携といった「土台」を固めてから、ツール選定や導入に進み、それに沿って運用していくことが成功のポイントだと考えています。
【実践編】MAツールで設定すべきシナリオ集
準備が整ったら、いよいよ設計をしていきます。顧客の行動に応じて自動的にアプローチするためには「シナリオ設計」が肝になります。ここでは、BtoBマーケティングでよくある3つの目的別に、具体的なシナリオ例をご紹介します。
シナリオ設計の基本となる考え方
優れたシナリオとは、「誰に」「何を」「どのタイミングで」届けるかが明確に設計されたものです。そして最も重要なのは、マーケティング部門の自己満足で終わらせず、必ず営業成果に繋がる具体的なゴールを設定することです。
シナリオ1:ウェビナー後のフォローアップを自動化し、商談機会を創出する
多くの企業が実施しているウェビナーですが、その後のフォローが手薄になりがちです。MAツールを使えば、熱量の高い参加者を逃さず商談に繋げることができます。
Step.1:参加者と欠席者でリストを分ける
ウェビナー終了後、参加状況に応じてリストを自動で振り分けます。これにより、それぞれの状況に合わせたコミュニケーションが可能になります。
Step.2:それぞれの関心度に合わせたメールを配信する
参加者:参加のお礼と共に、当日の資料とアンケートを送付。アンケートで「個別相談希望」と回答したリードは、即時営業担当に通知します。
欠席者:残念ながらご参加いただけなかった旨を伝え、録画動画と資料の案内、場合によっては個別にウェビナーの内容を伝える旨を送付します。
ゴール:温度感の高いリードを営業担当へスムーズに連携する
資料ダウンロードや個別相談申込といった熱量の高いアクションを起こしたリードを、その行動履歴と共に営業担当へ自動で通知。営業は顧客の関心事を把握した上で、最適なタイミングでアプローチできます。
シナリオ2:休眠顧客を掘り起こし、再アプローチする
過去に接点はあったものの、現在は活動が見られない「休眠顧客」。この眠っている資産をMAツールで掘り起こします。
Step.1:「休眠」の定義を明確にする
「過去180日間、メール開封もサイト訪問もないリード」のように、自社なりの休眠の定義を定め、該当するリストをMAツールで抽出します。
Step.2:特別な情報提供で再度関心を引く
通常のメルマガとは異なる、限定公開のレポートや、最新の業界トレンド解説といった「特別な情報」をメールで届け、反応を待ちます。ここで重要なのは売り込みではなく、価値提供に徹することです。
ゴール:反応があった顧客を育成プロセスに戻す
メールを開封したり、資料をダウンロードしたりしたリードは「休眠」から「アクティブ」へとステータスを自動変更し、再び育成シナリオの対象とします。忘れられていたリードが、再び有望な商談候補へと変わる瞬間です。
シナリオ3:「料金ページ閲覧」などの重要行動を捉え、即時アプローチする
購買意欲が最高潮に達した瞬間を逃さないためのシナリオです。
Step.1:ホットリードの行動を定義する
「料金ページを2回以上閲覧」「導入事例ページを3ページ以上閲覧」など、購買検討段階で特有の行動をスコアリングの対象として設定します。
Step.2:スコアリングで行動を点数化し、閾値を超えたら通知
設定した行動を取ったリードのスコアを自動で加算。合計スコアが事前に定めた閾値(例:100点)を超えた瞬間に、担当の営業へメールやチャットでアラートを自動送信します。
ゴール:営業が最良のタイミングでアプローチできる仕組みを作る
顧客がまさに比較検討しているその瞬間に、営業がアプローチできる仕組みを構築。これにより、競合に先んじて接点を持つことができ、商談化率、ひいては成約率の向上に大きく貢献します。
【Sells upの視点】優れたシナリオとは、マーケティング部門で完結せず、営業活動に直結するもの
シナリオ設計でよくある失敗は、メールを送って終わり、という自己満足に陥ることです。重要なのは、その一連のコミュニケーションが、最終的にどのような営業アクションに繋がるのかを設計の初期段階から営業部門とすり合わせることです。それをどのように設計するかが、成果を分けるポイントとなります。
MAツールの成果を最大化する応用のポイント
基本的なシナリオが回るようになったら、次は施策の精度を高め、成果を最大化させるフェーズです。ここでは、一歩進んだ活用のための3つのポイントを解説します。
スコアリング設計で変わるリードの質
スコアリングは、見込み顧客の行動や属性に点数を付与し、営業部門が優先すべきリードを明確にする仕組みです。例えば「資料請求+10点」「料金ページ閲覧+5点」「メール開封+2点」といった形で細かくルールを設定します。スコア設計が適切であれば、営業の工数を本当に有望なリードに集中させることができ、成果の質が大きく向上します。
行動データに基づいたスコアリングの具体例
「メール開封:1点」「セミナー参加:10点」「料金ページ閲覧:15点」のように、行動の「重み」を正しく設定することが重要です。特に、購買意欲との相関性が高いページの閲覧には高い点数を割り振るなど、自社の顧客行動を分析した上での設計が求められます。
スコアの有効性を定期的に見直す重要性
一度決めたルールが永続的に正しいとは限りません。「スコアは高いのに、商談化しない」といった事態が頻発する場合、スコアの定義が実態と乖離しています。営業部門からのフィードバックを基に、四半期に一度はスコアリングのルールを見直すなど、PDCAサイクルを回し続けることが、精度の高いリード選別を維持するポイントです。
営業部門と密に連携する方法
MAツールの成果は、営業部門との連携の質に比例します。密に連携を取り、共に商談獲得を目指しましょう。
リード引き渡しのルール(SLA)を明確にする
マーケティング部門と営業部門の間で「どのような条件を満たしたリードを営業にパスするのか」といったSLA(Service Level Agreement)を明確に定義しましょう。例えば「スコアが30点以上」「特定ページを複数回閲覧」など、客観的な基準と「スコアが何点以上のリードを、24時間以内に必ず架電する」といった具体的なルールを定めます。これにより、「リードの質が悪い」「フォローが遅い」といった不満や認識のズレを防ぎます。
MAの情報を営業活動に活かすための情報共有
MAツールで蓄積した「どのメールをクリックし、どのページを閲覧したか」といったリードの行動履歴や属性情報は、営業活動の質を高める資産です。営業担当がリードの関心テーマや過去のアクションを把握できるよう、情報共有やデータ構造を設計するとともに、営業現場からのフィードバックもMA施策の改善に活かしましょう。
施策の効果測定とROIの考え方
見るべきKPIは何か?活動指標と成果指標
MAツールの効果測定では、「メール開封率」「クリック率」「資料ダウンロード数」といった活動指標だけでなく、「商談化率」「成約率」「平均リード単価」などの成果指標も必ず追いましょう。両者のバランスを見て、施策全体のボトルネックを特定します。
費用対効果をどう判断するか
MAツールの導入・運用コストに対して、どれだけのリード獲得・商談創出・受注増加につながったかを数値で把握します。ROI(投資対効果)を定期的に算出し、経営層への説明材料や次年度の予算計画に活用しましょう。
【Sells upの視点】MAのデータはマーケティング部門の資産ではなく、事業全体の資産
MAツールで得られるデータは、マーケティング部門だけでなく営業・経営・カスタマーサクセス部門など、事業全体で活用すべき資産です。部門を横断した情報共有と意思決定に役立てることで、MAツールの価値を最大化できます。
自社に最適なMAツールの選び方
BtoB向けか、BtoC向けかを確認する
MAツールは、ターゲットとする顧客によって得意領域が異なります。BtoBであれば、企業単位でのリード管理やSFA連携が強いツールを。BtoCであれば、LINE連携やアプリのプッシュ通知など、個人向け機能が豊富なツールを選ぶのが基本です。
機能の多さよりも「自社で使いこなせるか」を重視する
高機能なツールは魅力的ですが、その分設定が複雑で、運用負荷も高くなる傾向があります。特に初めてMAツールを導入・活用する場合、機能の多さで選ぶと使いこなせずに失敗するリスクが高まります。自社の運用リソースや担当者のスキルレベルを冷静に判断し、「本当に必要な機能は何か」「直感的に操作できるか」という視点で選ぶことが重要です。
既存システム(SFA/CRM)との連携は可能か
すでにSFAやCRMを導入している場合、それらとスムーズにデータ連携できるかは必ず確認すべきポイントです。連携ができない、あるいは複雑な設定が必要な場合、手作業でのデータ移行が発生し、MA導入のメリットである効率化が損なわれてしまいます。
導入後のサポート体制は充実しているか
ツールを導入しても、最初のうちは設定や操作でつまずくことが必ずあります。そんな時に、電話やメールで気軽に相談できるか、セミナーや勉強会といった学習機会が提供されているかなど、ベンダーのサポート体制は非常に重要です。特に海外製ツールの場合は、日本語でのサポートがどの程度受けられるか、事前に確認しましょう。
【Sells upの視点】まずはスモールスタート。背伸びしたツール選びが失敗につながる
MAツールの導入で失敗する企業の多くが、最初から完璧を目指し、自社の身の丈に合わない高機能・高額なツールを選んでしまっています。成功のポイントは、必要最小限の機能を持つツールでスモールスタートし、成果や組織の成熟度に合わせて段階的に活用範囲を広げていくことです。
まとめ:MAツールを事業成果につなげるために
MAツールは、単なる自動化ツールではなく、営業成果を最大化するための「仕組み」として活用することが重要です。導入前の十分な準備、明確な目標設定、営業との連携、シナリオ設計、効果測定と改善。この一連の流れを愚直に回すことで、マーケティング活動を効率化させ、商談獲得にも効果を発揮します。
ツールに振り回されるのではなく、「成果」にこだわった運用を徹底し、事業成長につなげる手段としてMAツールを使いこなしてください。
MAツールの導入・活用の相談はSells upへ。
MAツールの導入や、導入後の成果最大化に課題をお持ちでしたら、ぜひSells upにご相談ください。50社以上の導入・活用を支援してきた担当者が貴社の状況・目標に向き合い、最適なツールの導入プラン / 統計知識を用いた活用プラン描き、戦略策定から実装 / 実行 / 効果測定までをご支援いたします。
CONTACT







